Contents
「雇い止め」とは?
「雇い止め」とは、「雇用期間が定められている労働契約」において、会社が契約を更新しない(または更新を拒絶する)ことにより、雇用期間の満了を理由として従業員との労働契約を終了させることをいいます。
一方、正社員など「雇用期間が定められていない労働契約」を会社が一方的に終了させること、および、「雇用期間が定められている労働契約」を期間の途中で会社が一方的に終了させることを「解雇」といいます。
雇い止めは法的に有効?無効?問題点は?
原則
原則として、雇い止めをすること自体は違法ではありません。
もともと、有期の雇用契約は、会社が臨時的・一時的な業務のための人員調整として行われることが多く、労使が互いに期間が満了することによって契約が終了することを承知しているためです。
例外
実際には、有期の雇用契約であっても、長年にわたって何回も契約が更新され、あるいは暗黙の了解で更新され続けている場合など、会社が契約の更新を期待させるような態度をとっていた場合には、従業員にとっては契約更新を期待するのが自然であり、契約が更新されないことによって、不測の損害を被る可能性があります。
そこで、このように契約の更新について高い期待が生じている従業員にとっては、「雇い止め」が実質的にみると「解雇」と異ならないものとして、法の保護を受けることができる場合があります。
このことは、労働契約法の第19条において定められています。
【雇い止めが法的に問題になる場合】
- 有期契約が、実質的にみて期間の定めのない契約と同視される場合
- 契約が更新されることに合理的な期待が生じている場合
上記の①または②に該当する場合には、雇い止めについて「解雇」に関する法理が適用されます。
そして、解雇は法的にみて非常にハードルが高く、解雇が法的に有効なものとして認められるためには、会社による雇い止めが「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当」であることが求められます。
さらに、解雇が無効であると認められる場合には、従前の有期契約と同じ労働条件で会社が申し込み、従業員がそれを承諾したものとみなされることになります(労働契約法第19条)。
.png)
有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
雇い止め法理に関する裁判例の判断要素
実際に、どのような場合に雇い止めが有効になるのかについて、明確な基準はありません。
そこで、雇い止めが法的に有効となるか無効となるかは、最終的には裁判で事案ごとに個別に決着が付けられるものです。
したがって、労務管理の実務において、雇い止めをするか否かの判断をする際には、過去の裁判例で示された判断基準をもとに、自社の状況に当てはめながら検証していくしかありません。
裁判例の判断要素
雇い止めに関する裁判例の傾向をみると、おおむね次の8つの判断要素をふまえながら、総合的に判断しています。
【雇い止めの判断要素】
- 業務の内容の性質(臨時的・一時的か)
- 業務の内容の責任・権限の度合い
- 契約の更新回数・通算期間
- 当事者の主観(更新を期待させる言動の有無)
- 更新の手続の厳格性
- 他の労働者の更新実績
- 契約における更新条件の記載
- その他
①業務の内容の性質(臨時的・一時的か)
業務の内容を正社員と比較した場合に、有期契約の従業員の業務内容が、明らかに臨時的・一時的なものであって、期間の経過によってその業務自体が消滅したような場合には、雇い止めが法的に有効になる可能性が高まるといえます。
例えば、年末年始の郵便局での郵便物の仕分けの業務や、新製品の発売に伴う工場での臨時増員、冬季限定の山小屋でのアルバイトなど、客観的にみて臨時的・一時的な業務であることが明らかな場合には、契約の更新に対する期待を保護する必要性に乏しいため、雇い止めについて法的な問題は生じにくいといえます。
裁判例では、私立大学の非常勤講師として、1年の期間を定めた雇用契約を21年間にわたり20回更新してきた語学教師に対する更新拒絶について、雇用契約は期間の定めがないものと同視することはできず、期間満了後も雇用関係が継続するものと期待することについて合理性があるものとは認められないとして、更新拒絶を適法と判断したものがあります(亜細亜大学事件 東京地方裁判所昭和63年11月25日判決)。
この裁判例では、専任教員(雇用期間の定めがない)と非常勤講師(雇用期間の定めがある)とで、職務・責任・拘束の度合いなどが明確に異なっていたことが、判断の分かれ目であったといえます。
②業務の内容の責任・権限の度合い
有期契約の従業員が、正社員とは異なる業務に従事しており、権限や責任の点で軽い場合は、更新に対する期待は低くなりやすいといえます。
反対に、正社員と同じ職務に従事しており、正社員と同様の役職に就くなど、権限や責任の度合いが同程度のレベルにある場合には、更新に対する期待が高まる(雇い止めが無効になる)可能性が高まるといえます。
③契約の更新回数・通算期間
一般に契約の更新回数が多く、通算期間が長くなるほど、従業員の更新への期待は高まるといえます。
逆に、一度も更新されていないのであれば、契約の更新に対する期待はそれほど高くないといえるでしょう。
しかし、更新回数が多いからといって、必ずしも雇い止めが無効になるものではなく、逆に、更新回数が少ないからといって問題がないとも限りません。
あくまで、他の判断要素とのバランスによって最終的な判断は変わります。
前掲の亜細亜大学事件では、20回もの更新がありましたが、雇い止めは適法と判断されました。
一方、期間を1年とする雇用契約を締結したトラック運転手に対する最初の更新時の雇止めについて、会社において過去に更新を拒絶した事例がなく、従業員も当然に契約が更新されるものと思ってきたことなどの事情から、雇い止めを無効とした裁判例があります(龍神タクシー事件 大阪高等裁判所平成3年1月16日判決)。
④当事者の主観(更新を期待させる言動の有無)
会社が有期雇用の従業員に対して、更新を期待させるような言動をしていた場合には、当然ながら、更新に対する期待は高まります。
採用に際して、会社側に長期継続雇用、本工への登用を期待させるような言動があり、期間の定めにかかわらず継続雇用されるものと信じて契約書を取りかわした事例で、解雇に関する法理を類推すべきとした裁判例があります(東芝柳町工場事件 最高裁判所昭和49年7月22日判決)。
⑤更新の手続の厳格性
契約の更新手続に関する運用が厳格になされておらず、いわゆる「暗黙の了解」で契約が更新されているような場合、雇い止めが法的に無効となる可能性が高まります。
【運用が厳格なケース】
- 更新の際、契約期間中の従業員の成績や勤怠を検証し、更新の有無を審査している
- 更新の際、従業員から更新希望の有無をヒアリングし、面談を実施している
- 更新の際、雇用契約書を取り交わしている
【運用が厳格ではないケース】
- 更新の際、契約期間中の従業員の成績や勤怠を検証していない
- 更新の際、従業員から更新希望の有無を確認せず、暗黙の了解で更新している
- 更新の際、雇用契約書を取り交わしていない、または、雇用契約書は一応取り交わしているが、更新日を過ぎてから締結している
⑥他の労働者の更新実績
雇い止めをする従業員と、近い立場にある他の従業員の雇い止めをした実績が少ない場合には、雇い止めが法的に無効になる可能性が高まるといえます。
逆に、同じ立場の従業員について、大多数が更新なく退職している状況であれば、従業員自身も更新に対する期待は低くなるといえます。
⑦契約における更新条件の記載
有期雇用の契約書においては、「不更新特約」といわれる、更新をしない契約であることを明記し、あるいは更新の上限について合意をしておき、その上限に達した時点で雇い止めをする場合があります。
この場合には、従業員の更新に対する期待は高まりにくいため、契約内容に従って行った雇い止めが無効と判断される可能性は低いといえます。
⑧その他
会社側の人員削減の必要性を判断要素とした裁判例として、独立採算制がとられている工場において、事業上やむを得ない理由により人員削減をする必要があり、その余剰人員を他の事業部門へ配置転換する余地もなく、臨時員全員の雇止めが必要であると判断される場合には、右希望退職者の募集に先立ち臨時員の雇止めが行われてもやむを得ないと判断したものがあります(日立メディコ事件 最高裁判所昭和61年12月4日判決)。
まとめ
雇い止めについては、法的に検証すべき点が多々あります。
契約の更新回数が多く、数年以上にわたって契約が更新されているような場合には、安易に雇い止めをするべきではなく、専門家などに相談しながら慎重な対応が求められるといえます。
.png)


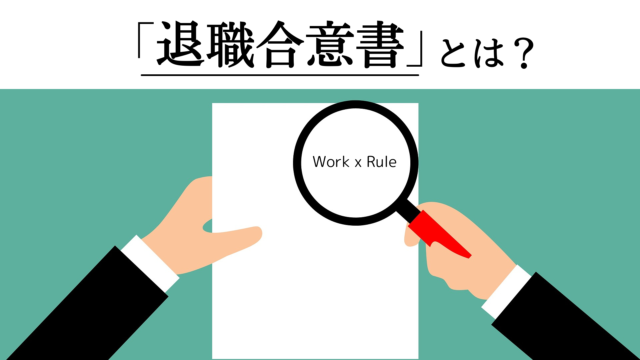
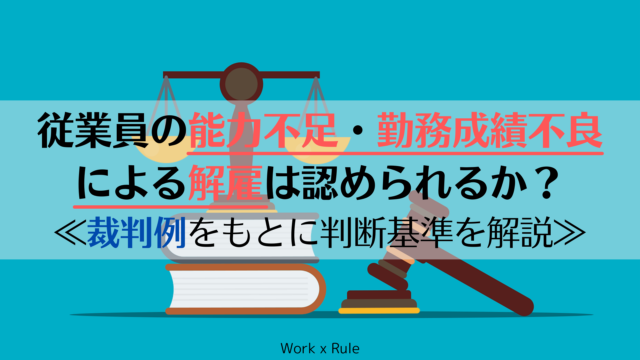
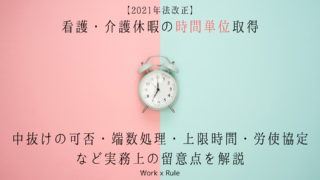
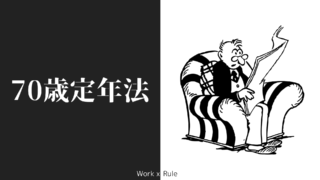
.png
)
.jpg)









