労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、1週間40時間と定めており、従業員が法定労働時間を超えて働く場合には、会社は割増賃金を支払うことが必要になります。
しかし、2つの規制が同時に存在しているために、会社や給与計算の担当者がルールを正しく理解しておかないと、割増賃金の支払い漏れや計算間違いが生じる可能性があります。そこで、今回は、法定労働時間や割増賃金の基礎知識を確認しつつ、1日8時間と1週間40時間が重複する場合について、いくつかの事例を踏まえながら、割増賃金の正しい把握方法を解説します。
【関連動画はこちら】
Contents
法定労働時間とは(1日・1週間)
1日の法定労働時間
労働基準法により、1日の法定労働時間は、「8時間」と定められています(法32Ⅱ)。
この8時間は、休憩時間を除いた実労働時間です。
また、「1日」とは、原則として、「午前0時から午後12時までの暦日24時間」をいいます(昭和63年1月1日基発1号)。
1週間の法定労働時間
労働基準法により、1週間の法定労働時間は、「40時間」と定められています(法32Ⅰ)。
なお、労働基準法の特例により、事業場によっては、1週間44時間が法定労働時間になることもありますが、説明を割愛します。
法定労働時間と割増賃金(残業代)
1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を超えて、従業員が働く場合には、会社は、その超えた時間に対する割増賃金の支払いが必要になります。
法定内残業と法定外残業における割増賃金(残業代)の違い
法定労働時間にかかわらず、会社が独自に定める始業・終業時刻に基づく労働時間を、「所定労働時間」といいます(いわゆる「定時」)。
この所定労働時間が、法定労働時間より短い場合には、所定労働時間超・法定労働時間未満の時間の労働は「法定内残業」にあたり、法定の割増賃金を支払う必要はありません(ただし、会社の判断によって支給しているケースはあります)。
例えば、所定労働時間が7時間の会社の場合、1時間の残業までは「法定内残業」、1時間を超える残業から「法定外残業」となりますので、会社は、その法定外残業をした時間に対して割増賃金を支払う必要があります。
1週間40時間の起算日はいつから(何曜日から)?通達をご紹介
1週間40時間の法定労働時間に関連して、「法定労働時間をどの曜日からカウントするか(起算日)」がとても重要になります。
どの曜日からどの曜日までを1週間の単位とするかによって、その1週間内の労働時間が変動するため、起算日を固定しておくことが必要になります。
行政通達(昭和63年1月1日基発1号)によると、労働基準法の「1週間」の定義は次のとおりです。
【1週間の定義】
1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。
上記の通達に従うと、1週間の起算日は、次のいずれかの日になります。
【1週間の起算日】
- 就業規則などに起算日の定めがある場合には、「その日」
- ①の定めがない場合には、「日曜日」
①の場合は、例えば、就業規則や雇用契約書などにおいて、「1週間の起算日は月曜日とする」などと定めている場合をいいます。
この場合には、その会社においては、1週間は「月曜日から日曜日まで」の単位となり、したがって、1週間40時間の法定労働時間についても、月曜日を起算日とした1週間の単位で時間外労働を把握することとなります。
また、①において何も定めていない場合には、②に従い原則どおり日曜日が起算日となりますので、1週間は「日曜日から土曜日まで」の歴週単位となります。
この起算日は、割増賃金の算定に大きく影響するので、自社の就業規則などを確認し、起算日を正確に把握しておくことが重要です。
1日8時間と1週間40時間のどちらを優先するのか?両者が重複する場合の優先順位
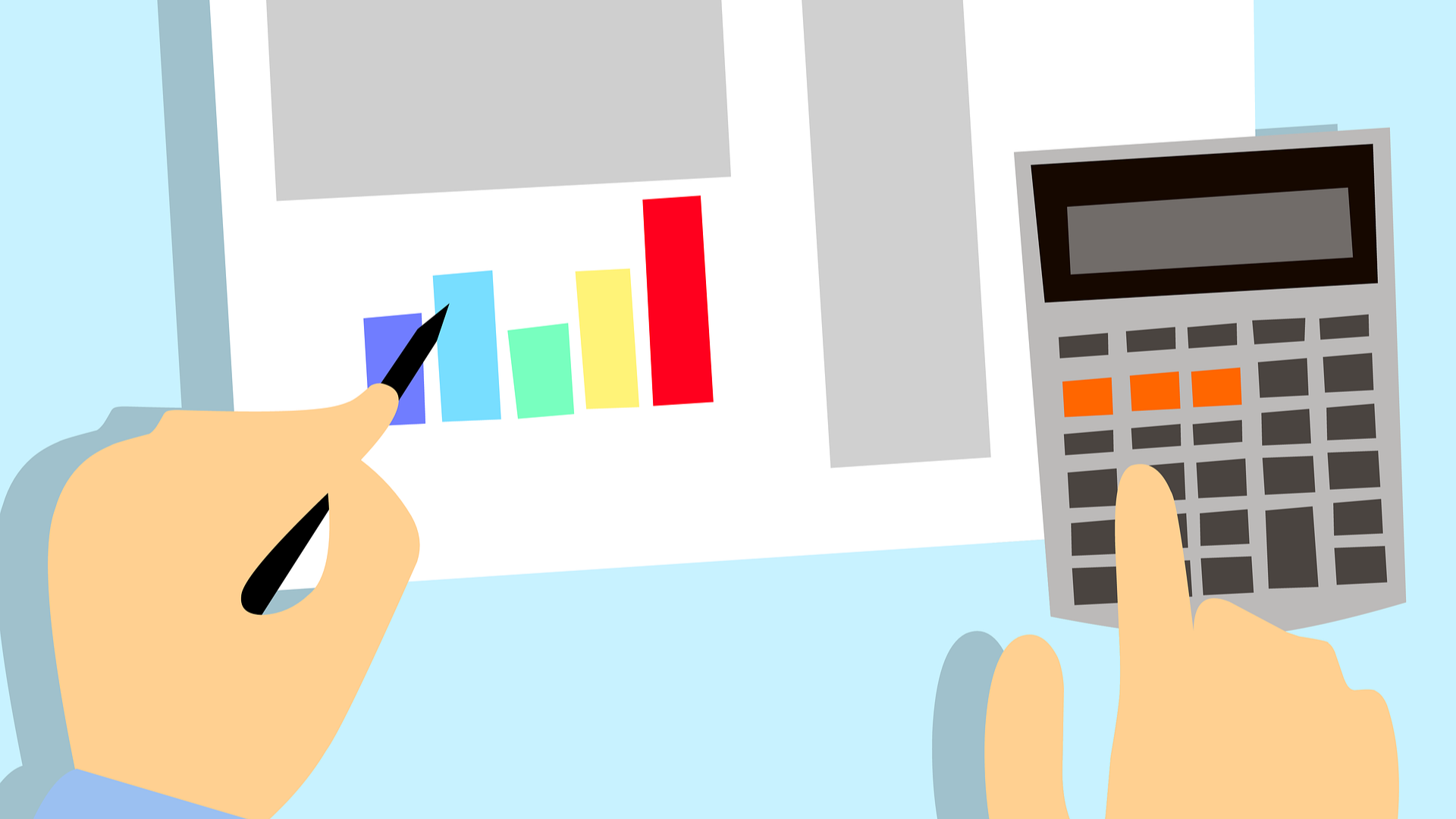 法定労働時間については、1日8時間と1週間40時間という2つの時間に基づく規制が、同時に存在しています。
法定労働時間については、1日8時間と1週間40時間という2つの時間に基づく規制が、同時に存在しています。
そこで、これらが重複する場面において、どちらの時間を優先して時間外労働を把握し、割増賃金を支払うべきかが問題となります。
この場合、結論としては、以下のとおり取り扱う必要があります。
【結論】
- 時間外労働の時間数は、「1週間ごと」に把握し、割増賃金の支払の有無を判断する。
- ある週において、1日8時間、または、1週40時間のいずれかを超える場合には、その「超えた時間数の多い(長い)方」の時間外労働をもとに割増賃金を計算する。
- 法定休日労働をした場合は、法定休日にかかる割増率(35%)に基づき割増賃金を計算し、その時間は1週間40時間の法定労働時間に含めない。
事例①(1日単位<1週間単位)
【所定労働時間】1日7時間(休憩除く)
【残業時間】なし
【週の起算日】月曜日
【所定休日】日曜日(週休1日制)
※1週40時間制の適用事業場とし、変形労働時間制の適用はないものとする
.png) この場合、まずは、1日単位でみて、法定労働時間を超えている時間を把握し、次に、1週間単位でみて、法定労働時間を超えている時間を把握すると分かりやすいでしょう。
この場合、まずは、1日単位でみて、法定労働時間を超えている時間を把握し、次に、1週間単位でみて、法定労働時間を超えている時間を把握すると分かりやすいでしょう。
「1日単位」でみたときの法定時間外労働
この事例では残業がありませんので、1日単位でみると、1日の法定労働時間である8時間の枠内に収まっています。
したがって、1日単位でみたときには、時間外労働は発生しておらず、したがって割増賃金を支払う必要はありません。
「1週間単位」でみたときの法定時間外労働
次に、1週間単位の労働時間を把握します。
1週間の労働時間は、「月曜日から土曜日までの6日間×7時間」で計算し、合計で「42時間」となります。
すると、1週間の法定労働時間である40時間を2時間超過していることが分かります。
結論
上記で把握した状況をもとに、1日単位の法定時間外労働である「0時間」と、1週間の法定時間外労働である「2時間」とを比較し、より多い(長い)方の「2時間」をその週における法定時間外労働として、割増賃金を計算し、支給することが必要です。
事例②(1日単位>1週間単位)
【所定労働時間】1日6時間(休憩除く)
【残業時間】月曜日に4時間、金曜日に4時間
【週の起算日】月曜日
【所定休日】土曜日・日曜日(週休2日制)
※1週40時間制の適用事業場とし、変形労働時間制の適用はないものとする
.png)
「1日単位」でみたときの法定時間外労働
この事例では月曜日と金曜日にそれぞれ4時間ずつ残業をしており、1日単位でみると、それぞれ1日の法定労働時間である8時間を2時間ずつ超えています(合計4時間)。
したがって、1日単位でみたときには、4時間の時間外労働が発生しており、したがって4時間分の割増賃金を支払う必要があります。
なお、6時間を超え8時間以内の時間帯の残業は、法定内残業であるため、原則として割増賃金を支払う必要はありません。
「1週間単位」でみたときの法定時間外労働
次に、1週間単位の労働時間を把握します。
1週間の労働時間は、「月曜日から金曜日までの5日間×6時間+残業時間8時間」で計算し、合計で「38時間」となります。
したがって、1週間単位でみたときには、時間外労働は発生しておらず、したがって割増賃金を支払う必要はありません。
結論
上記で把握した状況をもとに、1日単位の法定時間外労働である「4時間」と、1週間の法定時間外労働である「0時間」とを比較し、より多い(長い)方の「4時間」をその週における法定時間外労働として、割増賃金を計算し、支給することが必要です。
【発展】1週間40時間の法定労働時間と、法定休日労働との関係
労働基準法において、1週に1日確保するべき休日を「法定休日」といいます(法35Ⅰ)。
従業員が法定休日に働いた場合、会社は「35%」の割増賃金を支払う必要があります。
実務上、1週間40時間の法定労働時間を超える時間に対する割増賃金と、法定休日労働をした時間に対する割増賃金とを、しっかりと区別して理解しておくべき場合がありますので、事例をもとに解説します。
事例③
【所定労働時間】1日7時間(休憩除く)
【残業時間】土曜日に7時間
【週の起算日】月曜日
【所定休日】土曜日・日曜日(週休2日制)
※1週40時間制の適用事業場とし、変形労働時間制の適用はないものとする
.png)
「1日単位」でみたときの法定時間外労働
この事例では残業はありませんので、1日単位でみると、1日の法定労働時間である8時間の枠内に収まっています。
したがって、1日単位でみたときには、時間外労働は発生しておらず、したがって割増賃金を支払う必要はありません。
休日労働(土曜日)にかかる割増賃金
この事例では、土曜日に1日の休日労働がありますが、休日労働をしたとしても、なお週に1日の休日を確保することができているため、土曜日は法定休日労働とはならず、したがって、割増賃金は発生しません。
しかし、その休日労働によって、1週間単位でみたときの労働時間の合計が、1週間の法定労働時間である40時間を超える場合には、その超えた部分の時間は時間外労働となるため、割増賃金を支払わなければならないことに注意が必要になります(昭和63年3月14日基発150号)。
「1週間単位」でみたときの法定時間外労働
前述のとおり、1週間の労働時間は、休日労働の時間を含めて算定する必要があるため、「月曜日から土曜日までの6日間×7時間」で計算し、合計で「42時間」となります。
すると、1週間の法定労働時間である40時間を2時間超過していることが分かります。
ここで、休日労働を含めず、「月曜日から金曜日までの5日間」の労働時間だけで判断してしまうことのないよう、注意が必要です。
結論
上記で把握した状況をもとに、1日単位の法定時間外労働である「0時間」と、1週間の(休日労働を含めた)法定時間外労働である「2時間」とを比較し、より多い(長い)方の「2時間」をその週における法定時間外労働として、割増賃金を計算し、支給することが必要です。
事例④
【所定労働時間】1日7時間(休憩除く)
【残業時間】土曜日に7時間、日曜日(法定休日)に7時間
【週の起算日】月曜日
【所定休日】土曜日・日曜日(週休2日制)
※1週40時間制の適用事業場とし、変形労働時間制の適用はないものとする
.png)
「1日単位」でみたときの法定時間外労働
この事例では残業はありませんので、1日単位でみると、1日の法定労働時間である8時間の枠内に収まっています。
したがって、1日単位でみたときには、時間外労働は発生しておらず、したがって割増賃金を支払う必要はありません。
休日労働(土曜日)にかかる割増賃金
この事例では、1日の休日労働がありますが、週に1日の休日を確保することができているため、土曜日は法定休日労働とはならず、したがって、割増賃金は発生しません。
しかし、その休日労働によって、1週間単位でみたときの労働時間の合計が、1週間の法定労働時間である40時間を超える場合には、その超えた部分の時間は時間外労働となるため、割増賃金を支払わなければならないことに注意が必要になります(昭和63年3月14日基発150号)。
法定休日労働(日曜日)にかかる割増賃金
この事例では、日曜日が法定休日となりますので、法定休日労働に対する割増賃金が発生します。
この場合の割増率は、35%となります。
そして、法定休日労働に対して割増賃金を支払った場合には、その時間は、1週間の法定労働時間である40時間には含まれないため、1週間の法定労働時間は、日曜日を除く月曜日から土曜日の労働時間で判断します。
「1週間単位」でみたときの法定時間外労働
1週間の労働時間は、休日労働の時間を含めて算定する必要があるため、「月曜日から土曜日までの6日間×7時間」で計算し、合計で「42時間」となります。
すると、1週間の法定労働時間である40時間を2時間超過していることが分かります。
ここで、休日労働を含めず、「月曜日から金曜日までの5日間」の労働時間で判断することのないよう、注意が必要です。
結論
上記で把握した状況をもとに、1日単位の法定時間外労働である「0時間」と、1週間の(休日労働を含めた)法定時間外労働である「2時間」とを比較し、より多い(長い)方の「2時間」をその週における法定時間外労働として、割増賃金(割増率は25%)を計算し、支給することが必要です。
また、これに加えて、法定休日労働に対する割増賃金(割増率は35%)を計算し、支給することが必要です。
1週間40時間が月をまたぐ(月またぎ)場合の割増賃金(残業代)について
月によっては、1週間が月(賃金計算期間)をまたぐ場合があります。
このような場合、1週間の法定労働時間をリセットするような特例はありません。
したがって、原則どおり、暦週で(原則として日曜日から土曜日まで)、労働時間を把握します。
この場合、もし1週間で40時間を超える労働が発生した場合には、1週間40時間を超えることが確定したタイミングをもって、割増賃金を把握することになります。
もし、月内の時点で週40時間を超えている場合には、その超過した時間に対して、その月の給与において、割増賃金を支給することが必要になります。
まとめ
賃金の時効は2年間であるため、会社が割増賃金の計算を間違っていることが発覚した場合、最大で2年前まで遡って割増賃金を計算し直して支給する必要があります。
そのようなトラブルに発展しないためにも、会社の給与担当者が割増賃金の計算ルールを正しく理解しておくことが重要です。
.png)






.png
)
.jpg)









