Contents
解雇の予告とは?
会社は、労働基準法によって、従業員を解雇する場合には、「解雇日の遅くとも30日前」にその予告をしなければならない義務を負っています(労働基準法第20条第1項)。
この、法律によって会社に義務付けられている予告のことを、「解雇の予告」といいます。
労働基準法の趣旨は、会社による突然の解雇を認めてしまうと、たちまち従業員が生活に困窮してしまうおそれがあることから、せめて30日以上前に解雇の予告を義務付けることによって、従業員の保護を図ろうとするものです。
解雇予告の起算日
解雇予告をする際の実務上の留意点として、解雇予告の期間は、解雇の予告をした日の「翌日」から起算して数える必要があります(民法第140条)。
つまり、解雇の予告をした当日は、30日に含まれないことを意味します。
また、30日とは、歴日数であって、労働日数(出勤日数)ではない点にも留意が必要です。
例えば、6月30日をもって、会社が従業員を解雇しようとする場合には、原則として、会社は遅くとも「5月31日まで」に解雇の予告をする必要があります。
.png)
ただし、実務においては、後のトラブル(言った、言わないなど)を避けるためにも、書面で解雇の予告をすることが一般的です。
解雇予告手当とは?平均賃金との関係
解雇予告手当と即時解雇
会社は、前述の解雇の予告に代えて(解雇の予告をせずに)、「30日分以上の平均賃金」を支払うことによって、従業員を解雇することができます。
この「30日分以上の平均賃金」のことを、「解雇予告手当」といいます。
例えば、会社が「すぐにでも辞めてほしい」と考えている従業員がいる場合には、事前に解雇の予告をすることなく、解雇予告手当の支払いをもって、予告をしたその日に解雇することができます(これを「即時解雇」といいます)。
平均賃金の計算方法については後述します。
解雇の予告日数の短縮
解雇の予告と、解雇予告手当は、併用することができます。
例えば、解雇の予告日数である30日は、平均賃金を支払った場合には、支払った平均賃金の日数分だけ短縮することができます(労働基準法第20条第2項)。
.png)
解雇予告手当の支払日(支払時期・支払期限)と支払方法
解雇予告手当の支払日(支払時期・支払期限)
行政通達によると、解雇予告手当は、「解雇の申し渡し(解雇の通知)と同時」に支払う必要があるとされています(昭和23年3月17日基発464号)。
解雇予告手当の支払方法
解雇予告手当の支払方法については、特に法律上の規制はないため、通常の給料と同様に、現金や振り込みによって支払えば問題ありません。
なお、トラブルが原因で従業員が解雇予告手当の受領を拒んでいるような場合には、解雇予告手当を供託することをもって、会社が解雇予告手当を支払ったものとすることができます(昭和63年3月14日基発150号)。
解雇予告手当における平均賃金の計算方法
平均賃金とは?平均賃金の計算方法(原則)
平均賃金とは、解雇の予告をした日の直近3ヵ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額をいいます(労働基準法第12条)。
【平均賃金の計算方法(原則)】
直近3ヵ月間に支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総日数
「直近3ヵ月間」とありますが、賃金の締切日がある場合(つまり、一般的な月給のケース)には、「(解雇予告をした)直近の賃金の締切日」から起算した3ヵ月間で計算します。
賃金の総額とは?賞与や通勤手当(交通費)など諸手当の取り扱い
上記の「賃金の総額」には、以下の賃金を含まないものとされています。
【「賃金総額」に含まれない賃金】
- 臨時に支払われた賃金
- 3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
「臨時に支払われた賃金」とは、「支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するもの」をいいます(昭和22年9月13日発基17号)。
例えば、以下の賃金が該当します。
- 結婚手当(昭和22年9月13日発基17号)
- 私傷病手当(昭和26年12月27日基収3857号)
- 加療見舞金(昭和27年5月10日基収6054号)
「3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金」とは、例えば、年に2回(6ヵ月ごと)支払われる賞与などが該当します。
したがって、3ヵ月の間に、たまたま賞与を支給していたとしても、賃金総額には含めずに平均賃金を計算します。
上記の賃金以外は、基本的に賃金の総額に含まれると考えてください。
例えば、通勤手当(交通費)、皆勤手当、家族手当、時間外労働手当などは、すべて賃金総額に含めて平均賃金を計算します。
平均賃金の計算例
平均賃金の計算例を紹介します。
【平均賃金の計算例】
- 3月31日付けで従業員のAさんを解雇する
- 3月21日に解雇の予告をし、同時に解雇予告手当を支払う
- 賃金締切日は毎月15日締め
- Aさんの直近3ヵ月間の賃金総額は、900,000円
平均賃金の計算
まず、3月21日に解雇予告をしており、その直前の賃金締切日は3月15日であるため、3月15日からさかのぼって、3ヵ月間の賃金の総額と日数を把握します。
| 計算期間 | 日数 | 賃金額 |
| 2/16~3/15 | 28日 | 300,000円 |
| 1/16~2/15 | 31日 | 300,000円 |
| 12/16~1/15 | 31日 | 300,000円 |
| 合計 | 90日 | 900,000円 |
平均賃金は、3ヵ月間の賃金総額「900,000円」を、その総日数「90日」で割ることによって、1日あたり1万円という結果になります。
解雇予告手当の計算
解雇予告の期間は、予告をした日の翌日(22日)から起算して、31日まで、10日となります。
そこで、法律が求める30日前の予告と比べると、20日短いため、会社は、20日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
そこで、平均賃金の1万円に20日を乗じた「20万円」が、解雇予告手当として最低支払わなければならない金額となります。
平均賃金と解雇予告手当の端数処理
平均賃金の端数処理
平均賃金の計算の結果生じた端数については、行政通達により、「銭未満を切捨て」して処理することとされています(昭和22年11月5日基発232号)。
例えば、3ヵ月間の賃金総額が890,000円であった場合には、90日で割ると、「9,888円8888…」という計算結果になります。
この場合の端数処理は、銭未満を切り捨てるため、平均賃金は「9,888円88銭」となります。
解雇予告手当の端数処理
解雇予告手当の計算の結果生じた端数処理については、「円未満の端数を四捨五入」することとされています(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条)。
平均賃金が9,888.88円、支払日数が19日の場合、解雇予告手当は「187,888.72円」となり、円未満の端数(0.72円)を四捨五入することにより、解雇予告手当は「187,889円」となります。
解雇予告手当の最低保障額
解雇予告手当には、最低保障額、つまり、「この金額を下回ることができない」という最低ラインが決められています。
最低保障額は、「3ヵ月間の賃金総額を、その労働日数(出勤日数)で割った額の6割」とされています。
この最低保障額は、日雇いや出来高などで働いている従業員について問題になります。
【解雇予告手当(1日分)の最低保障額】
直近3ヵ月間の賃金総額 ÷ 労働日数(出勤日数) × 60%
以下、計算例を紹介します。
【解雇予告手当の計算例】
- 従業員のBさんの直近3ヵ月間の賃金総額は、900,000円
- 直近3ヵ月間の総日数は、90日
- 直近3ヵ月間の出勤日数は、50日
まず、原則的な平均賃金は、
900,000円÷90日=10,000円
となります。
次に、最低保障額を計算すると、直近3ヵ月間の出勤日数は50日であったため、
900,000円÷50日×60%=10,800円
となります。
最後に、平均賃金と最低保障額を比較し、「高い方の金額」を解雇予告手当とする必要があるため、結論として、この場合の解雇予告手当は「10,800円」となります。
例えば、日雇いの場合で、3ヵ月間の賃金総額が10万円、総日数が90日、出勤日数が10日である場合、原則どおり平均賃金を計算すると、約1,111円となってしまいます。
そこで、最低保障額を設けることにより、この場合には平均賃金を6,000円(10万円÷10日×60%)に引き上げることにより、従業員を保護しようとするものです。
パート(アルバイト)の場合の解雇予告手当の計算方法
労働基準法の解雇予告や解雇予告手当の定めは、原則としてパートやアルバイトなど、雇用形態にかかわらず適用されます。
ただし、次の場合には、法律を適用しない(「適用除外」という)ことと定められています(労働基準法第21条)。
【解雇予告の適用除外】
- 日々雇い入れられる者
- 2ヵ月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者
上記の従業員は、もともと長期の雇用を前提とされておらず、短い期間で退職することが予定されているため、解雇予告の対象から外れています。
ただし、以下の場合には、解雇予告をしなければならなくなると定められているため、注意が必要です。
- ①に該当する者が1ヵ月を超えて引き続き雇用される場合
- ②または③に該当する者が所定の期間を超えて引き続き雇用される場合
例えば、最初は2ヵ月の期間で契約していたが、契約を更新することとなり、さらに2ヵ月の期間で契約を更新した場合には、その後解雇する際に解雇予告(または解雇予告手当)が必要になります。
試用期間中は解雇予告手当が必要か?
法律上、試用期間中は、「14日以内」であれば、解雇予告(または解雇予告手当)が不要であるとされています(労働基準法第21条)。
したがって、入社後14日を超えた場合には、解雇予告(または解雇予告手当)が必要になります。
例えば、会社の就業規則上の試用期間が3ヵ月である場合に、「3ヵ月までは解雇予告は必要ない」という勘違いをしてしまうことがあるため、留意してください。
解雇予告および解雇予告手当の支払が法律上不要となる場合
解雇予告および解雇予告手当の支払を、法律上免れることができる場合として、次の2つのがあります(労働基準法第12条)。
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由にもとづいて解雇する場合
①の場合は、地震などの災害時において、会社の事業が継続できないような場合にまで、会社が従業員の保護を図ることは無理があるためです。
②の場合は、従業員がその重大な非違行為によって、懲戒解雇されるような場合にまで、従業員の保護を図る必要性に乏しいためです。
ただし、いずれの場合も、会社の独断によることはできず、会社は、労働基準監督署に対して、解雇予告の適用を除外するよう申請し、認定を受ける必要があります。
この、労働基準監督署に対する申請を、「解雇予告の除外認定申請」といいます。
認定を受けたからといって、解雇そのものが法的に有効であることのお墨付きにはならない点に注意が必要です。
解雇予告手当にかかる社会保険料・所得税の取り扱い
社会保険料の取り扱い
解雇予告手当は、社会保険料の対象となる賃金には含まれません。
これは、解雇予告手当は単に法律の手続上必要となるものであって、社会保険料の対象となる「労働の対償」としての賃金ではない(働いたことに対する対価ではない)ためです。
税金の取り扱い
解雇予告手当の所得税上の取り扱いは、退職(解雇)に伴って支払われるものであることから、給与所得ではなく、「退職所得」として取り扱うこととされています。
労働基準法第20条(解雇予告手当)の罰則と付加金
労働基準法上の罰則
労働基準法上、解雇予告をしない、もしくは適正に解雇予告手当を支払わない場合には、「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます(労働基準法第119条)。
付加金の支払命令
会社が解雇予告手当を支払わない場合、従業員は裁判において、支払われなかった解雇予告手当の2倍の額を付加金として請求することができます(労働基準法第114条)。
これは、解雇予告手当の支払いを会社が怠ったことに対する、いわばペナルティとして支払いを命じられるものです。

.png)

.png)


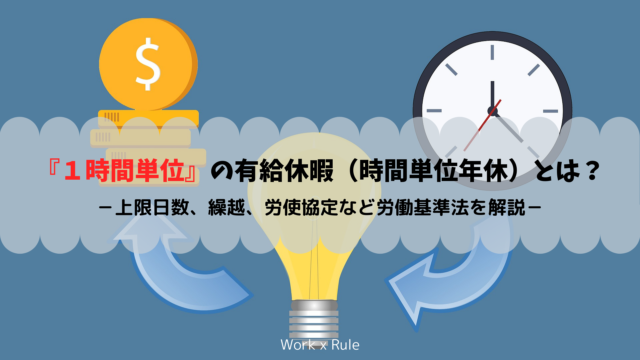

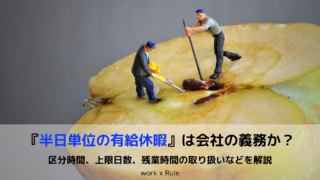
.png
)
.jpg)








