2019年7月現在、労働基準法で定められている賃金の時効を、現行の2年から5年に延長するかどうかについて、法律の改正に向けた議論が行われています。
この議論は、2020年4月1日に「民法」という法律の時効が改正されることに伴って、行われているものです。
今回の記事では、賃金の時効が延長されることによって、労務管理にどのような影響があるのか、民法の改正内容にも触れながら、解説します。
Contents
労働基準法の時効の改正はいつから(施行日)?
2019年7月時点では、労働基準法が改正されるかどうか、もし改正されるとして、いつから施行されるのかについては決まっていません。
ただし、この議論が2020年4月1日に改正される民法に合わせたものであるため、労働基準法が改正される場合には、民法の施行日と足並みを揃える(つまり民法と同じく2020年4月1日になる)可能性が高いといえます。
今後の法改正の方向性について
厚生労働省に設置された有識者の会議である「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」より、2019年7月1日付で、次のとおり意見が出されています。
要約すると、今後の方向性として、「見直しが必要」と考えられていますが、法律の改正による社会経済への影響の大きさを考えながら、実際に延長する時効の期間については、引き続き検討していく方向であることがうかがえます。
- (略)将来にわたり消滅時効期間を2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる。
- ただし、労使の意見に隔たりが大きい現状も踏まえ、消滅時効規定が労使関係における早期の法的安定性の役割を果たしていることや、大量かつ定期的に発生するといった賃金債権の特殊性に加え、労働時間管理の実態やそのあり方、仮に消滅時効期間を見直す場合の企業における影響やコストについても留意し、具体的な消滅時効期間については引き続き検討が必要。
労働基準法の改正の内容は?賃金の時効とは?
労働基準法が改正される場合、主な改正点は、「賃金の時効が2年から5年に延長される」というものです。
「賃金の時効」とは、すごく簡単にいうと、「従業員から会社に対して、給料を支払うよう、請求できる期間」のことをいいます。
現行の労働基準法では、賃金の時効は「2年」と定められています(労働基準法第115条)。
【労働基準法の時効】
- 賃金…2年
- 退職金…5年
- その他の請求権…2年
つまり、もし会社が従業員に対して支払うべき給料を支払っていなかった場合、従業員から何の請求もないまま2年間放っておくと、時効が成立し、その後はこの給料を請求することができなくなるということです。
たしかに、給料を2年も支払わない会社は、そうはないでしょう。
しかし、ここでいう「賃金」には、「残業代」も含まれます(残業代は、正確には「割増賃金」といいます)。
世の中には、何らかの事情によって、残業代が正しく支払われていないことにより、従業員から会社に対して、残業代を支払うよう裁判を起こしている事例も数多くあります。
このとき、賃金の時効期間が重要になります。
つまり、現行の法律では、従業員は会社に対して、過去2年分の残業代をまとめて請求することができます。
裏返せば、過去2年より前の残業代は、時効によって消えてしまっているため、もはや請求することができない、ともいえます。
はい。
このトラブルは、労務トラブルの中でも、比較的多い部類であるといえます。
法律どおり適正に支払われていない残業代のことを、「未払い残業代」や「不払い賃金」といったりもします。
労働基準監督署の「監督指導による賃金不払残業の是正結果(2018年8月10日公表)」によると、労働基準監督署が残業代を支払うよう命じた企業数は、1,870企業(前年度比 521企業の増加)、それによって支払われた割増賃金の合計額は、446億4,195万円(同 319億1,868万円の増加)となっています。
これをみると、未払残業代がいかに大きな社会問題になっているのかが分かるでしょう。
このような現状の中、賃金の時効が延長されれば、従業員から会社に対して請求する未払残業代の額が飛躍的に増加するとともに、これに伴って関連する裁判も増加することが予想されます。
民法の改正内容と、賃金の時効との関係性

それでは、まず、民法の改正内容について説明しましょう。
民法の改正内容
2017年5月26日に「民法の一部を改正する法律」が国会で成立したことを受けて、2020年4月1日に民法が改正されます。
これにより、民法に定められている「消滅時効の期間」が以下のように改正されます。
【消滅時効の期間(民法改正)】
- 権利を行使することができる時から「10年」
- 権利を行使することができることを知った時から「5年」
「消滅時効」とは、法律上の権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その期間の満了をもって、その権利を消滅させる制度をいいます。
改正前の民法には、「短期消滅時効」という、通常の消滅時効よりも短い期間(1年や3年など)の消滅時効が存在しており、制度がとても複雑だったのですが、改正により短期消滅時効は廃止され、上記の2つの消滅時効に統一されることになりました。
民法の改正内容と、賃金の時効との関係性
民法の改正に伴って、賃金の時効を2年と定めている労働基準法の定めが、民法と矛盾するのではないか、という議論が始まりました。
もともとの経緯として、賃金については、改正前の民法では、消滅時効が「1年」と定められていた(民法第174条)ところ、「労働者を保護する」という観点から、労働基準法によって、わざわざ「2年」に延長して定めたという背景があります。
そして、労働基準法は、民法に優先して適用されるため(これを、「特別法」といいます)、これまでは賃金の消滅時効は2年とする実務が行われてきました。
しかし、民法の改正に伴い、「民法では5年、労働基準法では2年」という、当初の趣旨とは矛盾することになり、労働者保護の観点からは、民法の改正に合わせて、労働基準法の賃金の消滅時効を、2年から5年に延長するべきとする議論が始まりました。
賃金の時効の起算日(起算点)はいつ?
時効の期間を正しく理解するためには、時効がいつから(どの日から)スタートするのかを知っておく必要があります。
この、時効期間のカウントがスタートする日のことを、「時効の起算日(起算点)」といいます。
そして、賃金に関する消滅時効の起算日は、「給料の支払い日(給料日)の翌日」です。
勤務した日や、給料の締め日などではありませんので、誤解のないようにしましょう。
したがって、労働基準法が民法に合わせて改正された場合、従業員は、5年前の給料日までさかのぼって、未払いの賃金や残業代などを請求することができることになります。
給料日は毎月訪れますので、それぞれの給料日から、それぞれの時効のカウントが始まることになります。
有給休暇の時効も2年から5年に延長される?
賃金の時効の議論に伴って、「有給休暇の時効はどうなるのか?」という点についても話題にあがっています。
「有給休暇の時効」についても、現在の労働基準法では「2年」と定められています。
これによって、有給休暇は2年まで繰り越すことができることとされています。
つまり、有給休暇は、前年度に発生したもの(勤続年数により、最大20日)と今年度に発生したもの(最大20日)を足した日数(最大40日)をもつことができます。
賃金の時効期間に改正があった場合には、この有給休暇の時効にも影響を及ぼすのかどうか、ということが話題になっています。
そうですね。
ですが、残念ながら、現時点では、どうやら有給休暇の時効については改正されない方向性で話が進んでいるようです。
検討会によると、以下の理由から、「必ずしも賃金請求権と同様の取扱いを行う必要性がない(=改正はしない)との考え方で概ね意見の一致がみられる」としています。
- 有給休暇に関しては、そもそも年休権が発生した年の中で取得することが想定されている仕組みであり、未取得分の翌年への繰越しは制度趣旨に鑑みると本来であれば例外的なものであること
- 法律を改正することにより、有給休暇の取得率を向上させるという、政策の方向性に逆行するおそれがあること
書類の保存期間への影響
労働基準法の賃金の時効が改正された場合には、これに伴って、労働基準法における書類(賃金台帳など)の保存期間についても影響を及ぼします。
書類の保存期間は、労働基準法により「3年」と定められているため、賃金の時効が今よりも延長される場合には、それに伴って保存期間も延長されるでしょう。
書類の保存期間に違反すると、罰則があります。
したがって、法改正があった場合には、誤って書類を廃棄してしまわないよう、社内規程や管理の見直しなどが必要になるでしょう。
まとめ
実際に法律が改正され、賃金の時効が延長されることになれば、労務管理への影響はとても大きいと考えます。
もともと、時効云々に関わらず、会社は適正に残業代を支払うべき立場にありますので、わざわざ騒ぐ必要性はないのではないか、という議論はさておき、現実問題として、会社はさらに厳格・厳密な労務管理を求められることになるでしょう。
もともと、未払いの残業代については、2年という期間でも多額になるリスクが十分にあり、会社として適正な労務管理が必要になることに変わりはありません。
今回の法改正を機に、改めて労務管理のあり方を見直されてはいかがでしょうか。
.png)
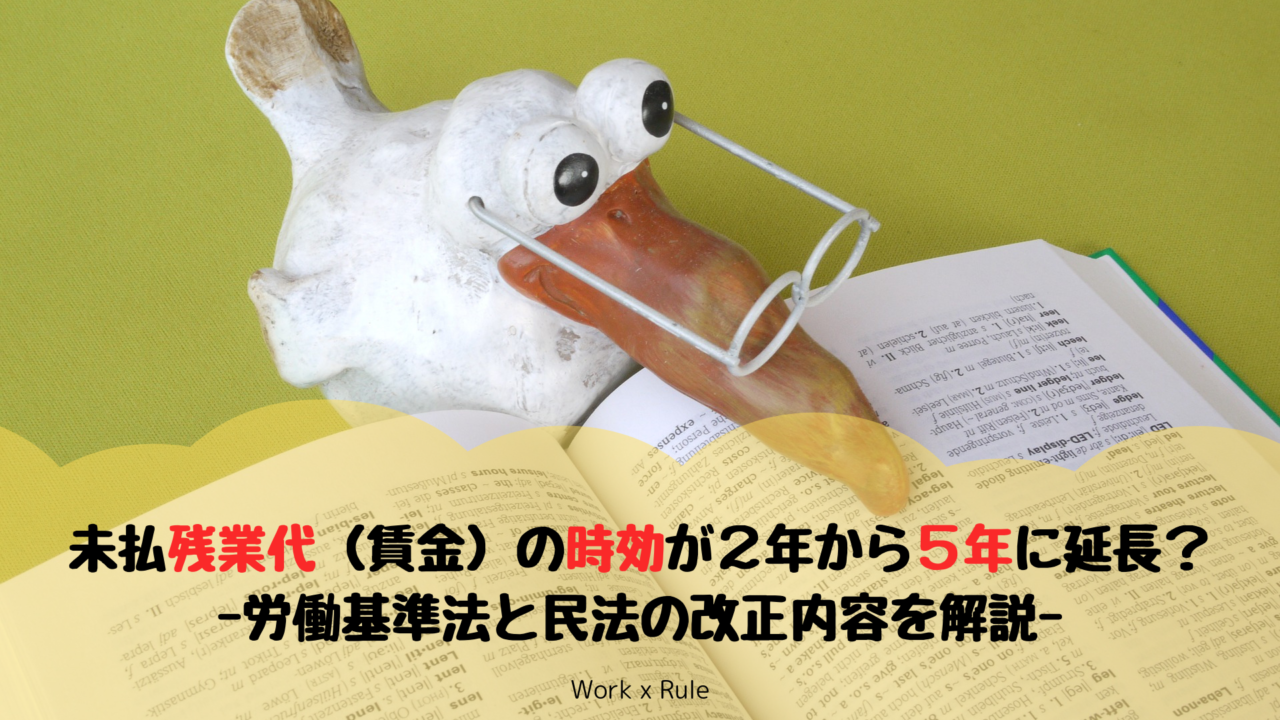
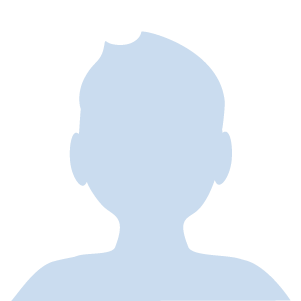
.png)





.png
)
.jpg)









