会社組織では一般的に、従業員数の増加に伴い、配置転換に伴う転勤や業務内容の変更など、人事異動を命令する場面が増加します。
そして、従業員の中には、会社からの人事異動命令に対して、当該命令に従わず、命令を拒否する従業員が現れることがあります。
このような場合に、会社は人事異動命令を拒否した従業員をどのように取り扱うべきか、問題となることがあります。
会社にとっては、最終的に従業員を解雇することができないとなると、人事権は有名無実のものとなり、人事異動命令に実効性がなく、会社内の秩序を保つことができなくなる恐れがあります。
一方で、従業員にとっては、子育てや介護など私生活で重大な問題を抱えているような場合にまで、会社の命令を拒否することができないとなると、あまりに不利なようにも思えます。
そこで今回は、転勤命令のケースを題材に、法的な観点から、両者のバランスがどのように図られていくべきかを解説します。
Contents
転勤命令の有効性を判断するためのポイント
転勤命令が法律的に有効と認められるかどうかについては、労働基準法などの法律の条文には明記されていません。
そこで、過去の裁判例や法律の解釈をもとに検討する必要があります。
転勤命令が法律的にみて有効であれば、従業員は命令を拒否することができず、これに対して会社が解雇などの処分を行うことは問題ありません。
一方、転勤命令が法律的にみて有効でない場合には、命令を拒否した従業員に対する解雇などの処分が権利の濫用とみなされ、違法となることがあります。
実務上は、転勤命令の有効性を判断する際には、主に次の3つのポイントを中心に検討するとよいと考えます。
【A】
就業規則や労働契約書等において、転勤を伴う人事異動を命令する根拠となる定めがあるかどうか〔労働契約上の根拠規定の有無〕
【B】
転勤命令が、業務上の必要性があるかどうか(理由において合理的であり、かつ、不当な動機はないか)〔業務上の必要性の有無〕
【C】
従業員にとって、重大な不利益がないかどうか〔重大な不利益の有無〕
【A】労働契約上の根拠規定の有無
まず、会社が転勤命令を始めとする人事異動命令を行うためには、そもそも、会社と従業員との間の労働契約において、そのことを定めていなければなりません。
そして、労働契約は、就業規則や労働条件通知書、雇用契約書などで行われることが一般的です。
例えば、勤務地を限定した労働契約を結んでいる場合など、転勤がないことが契約上明らかな場合には、会社による転勤命令は認められません。
したがって、会社は、転勤に限らず、どのような人事異動命令であっても、まずはその命令の根拠となる定めが就業規則などに記載されているかどうかを確認することが必要です。
参考に、会社による転勤命令を定めた就業規則の規定例をご紹介します。
就業規則 第○条
会社は、業務上必要がある場合に、配置転換、転勤または出向を命じることができ、従業員はこれを拒むことができない。
もし、就業規則などに人事異動命令に関する定めがない場合には、どうすればいいのでしょうか。
この場合には、同様の業務に就いている他の従業員にも、同じように転勤命令が出されている実績があるかどうか、つまり、会社内で同様の転勤が慣例となっているかどうかが判断材料となり得ます。
例えば、支店が複数ある会社の総合職であれば、他の支店することが事実上多くあり、それが慣例になっているような場合には、転勤命令が認められる可能性は高まるでしょう。
【B】業務上の必要性の有無
次に、転勤命令について、業務上の必要性があるかどうかが問題になります。
「配転命令の業務上の必要性」については、他の従業員ではどうしても替え難い、というような高度の必要性までは要求されないと解釈されています(東亜ペイント事件 昭和61年7月14日最高裁判所判決)。
一般的には、従業員の適正配置や業務運営の円滑化を図るなどの事情があれば、業務上の必要性は肯定されると解されますので、あまり神経質になる要件ではないと考えます。
ただし、そこにやや特殊な事情が混在している場合には、以下の裁判例のように、業務上の必要性が否定されるケースもあります。
業務上の必要性が否定された事例(会社側が敗訴した判決)
①NTT西日本事件(平成21年1月15日 大阪高等裁判所判決)
企業の構造改革に伴い既に一定の業務に就いていた従業員に対して、新たに新幹線通勤や単身赴任の負担を負わせる配転について、業務上の必要性が否定された。
②C株式会社事件(平成23年12月16日 大阪地方裁判所判決)
会社の解雇撤回後に職場復帰する従業員に対して命じられた、大阪から名古屋への配転について、業務上の必要性が否定された。
また、会社の転勤命令に、そもそも不当な目的や動機がある場合には、当然ながら、業務上の必要性は認められません。
不当な目的がある場合の典型例としては、従業員を退職に追い込むためや、嫌がらせ目的の転勤命令が挙げられます。
不当な目的・動機があると判断された事例(会社側が敗訴した判決)
①フジシール事件(平成12年8月28日 大阪地方裁判所判決)
開発業務の管理職に従事していた従業員が退職勧奨に応じなかったため、肉体労働を要する職場へ配転命令を出したことについて、当該命令は嫌がらせ目的であり、権利の濫用とみなされ、配転命令は無効と判断された。
②マリンクロットメディカル事件(平成7年3月31日 東京地方裁判所判決)
社長の経営方針に批判的言動をとった報復としての転勤命令が、無効と判断された。
【C】重大な不利益の有無
 最後に、転勤によって従業員が受ける不利益の程度を考慮する必要があります。
最後に、転勤によって従業員が受ける不利益の程度を考慮する必要があります。
裁判例では、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」に該当するかどうか、という基準を用いています。
どのような不利益がこれに該当するのかは一概には線引きできませんので、裁判例をもとに判断する必要があります。
「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」とは認められなかった判決(会社側が勝訴した判決)
①東亜ペイント事件(昭和61年7月14日 最高裁判所判決)
家庭の事情を理由に、転居を伴う転勤には応じられないとして、2度にわたり転勤命令を拒否した従業員に対して、会社が就業規則に基づき行った懲戒解雇は有効であると判断された。
裁判所は、転勤によって家族との別居を余儀なくされるという家庭生活上の不利益は、転勤に伴い、一般に受け入れるべき程度のものであると判断した。
②帝国臓器製薬事件(平成11年9月17日 最高裁判所判決)
配転に応じると単身赴任せざるをえないという事情だけでは、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」とは認められないとした。
③ケンウッド事件(平成12年1月28日 最高裁判所判決)
配転によって通勤時間が片道約1時間長くなり、保育園に預けている子供の送迎等で支障が生じる事情では、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」とは認められないとした。
「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」と認められた判決(会社側が敗訴した判決)
①日本電気事件(昭和43年8年31日 東京地方裁判所判決)
転勤命令を受けた労働者が、病気の家族を複数人、一人で看ており、さらに生計の中で当該労働者の収入が大きな割合を占めている場合において、転勤命令が無効と判断された。
②明治図書出版事件(平成14年12月27日 東京地方裁判所判決)
重度の病気の3歳以下の子供2人を、自らまたは配偶者らと看護していた場合に、東京から大阪への転勤命令を無効と判断した。
③NTT東日本事件(平成21年3月26日 札幌高等裁判所判決)
老齢で障害をもつ両親と同じ苫小牧市内に住み、両親の介護をしていた従業員が、東京への転勤を命じられ、これを拒否した事件。
従業員が単身赴任した場合には、従業員の妻らが両親の介護をすることになるが、従業員の妻と従業員の両親の関係からそれは困難であるうえ、従業員が両親を連れて東京に転居することも困難であるとして、会社の転勤命令を違法と判断した。
④ネスレ日本事件(平成18年4月14日 大阪高等裁判所判決)
老齢で徘徊癖のある母親と同居している従業員が、姫路工場から霞ヶ浦工場への転勤を命じられ、これを拒否した事件。
昼間は従業員の妻が従業員の母親の見守りや介助を行い、夜間は従業員自身が母親の見守りや介助を行っていたという事情があった。
そして、従業員が単身赴任した場合には、昼夜ともに従業員の妻が従業員の母親の見守り、介助を行うことになるが、それは実際上不可能であり、また、従業員が母親を連れて一家で転居することも困難であるとして、会社の転勤命令は違法であると判断した。
裁判例をみると、従業員の家族について介護や重大な病気があり、それによって一家を連れての転勤や単身赴任が不可能であるというようなケースでは、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」があると判断され、会社の転勤命令が違法となる可能性が高まるといえます。
まとめ
会社による転勤命令や人事異動命令については、一般に会社は従業員に比べて強い権限を持っていると解釈されています。
これは、日本の雇用システムでは、終身雇用が未だに根強く、会社の人事権にある程度の裁量を持たせる必要性があるためです。
しかし、昨今では育児介護休業法(第26条参照)などを受けて、従業員側の事情として、育児や介護の状況を尊重すべきとする世論が高まっており、転勤命令の有効性の判断についても、以前より従業員側の個別事情を考慮する風潮が徐々に高まってきているように感じます。
よって、会社は、大きな労務トラブルを防止するためには、転勤を命じる従業員について、その家庭事情を事前にしっかりとヒアリングしておき、会社側の必要性と従業員側の家庭事情とのバランスを図りながら、できる限り従業員の納得・理解を得たうえで転勤させるよう配慮していくことが求められると考えます。
(参考)育児介護休業法 第26条
(労働者の配置に関する配慮)
事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。
.png)

.png)
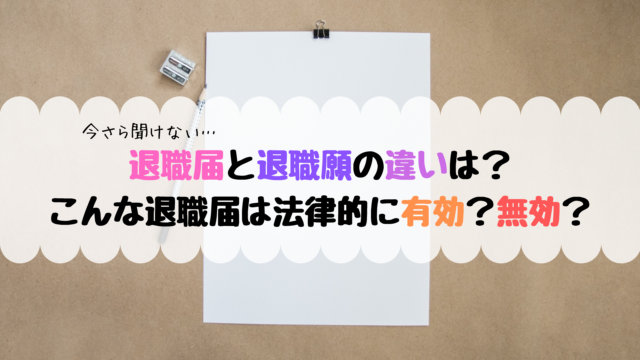

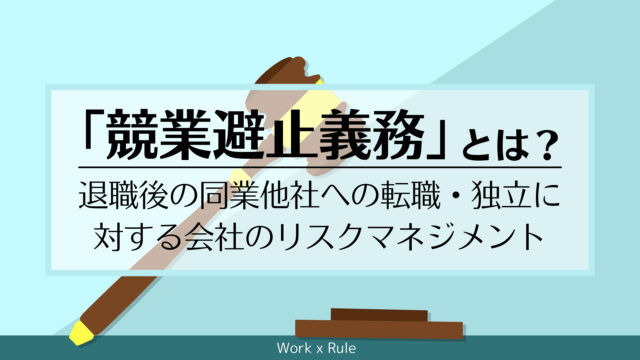


.png
)
.jpg)









