Contents
はじめに
近年、日本の終身雇用のあり方に変化が生じており、今後は雇用が流動化していくことに伴って、転職や独立・起業が増加することが見込まれます。
会社の労務管理においては、せっかく時間と費用を投じて育成した従業員が、自社のノウハウや技術をもって、競合する同業他社に転職してしまうことは、同業他社の競争力を高めることにつながりかねません。
さらには、転職や独立に伴って、顧客情報や製造技術など、会社の秘密情報が流出することによっても、営業上の損害を被るリスクがあります。
そこで、会社のリスクマネジメントのひとつとして、従業員の同業他社への転職や独立・起業について、一定の制限をかける必要性が生じることがあり、これは退職後の従業員に対して「競業避止義務」を課すことができるかどうかという点で問題になります。
競業避止義務とは?
競業避止義務とは?
「競業避止義務」とは、一般に、従業員が、同業他社などで会社の不利益になるような競業行為をしてはならない義務をいいます。
ここでいう「競業行為」とは、例えば、従業員が会社を退職した後に、同業他社に転職し、在職中に知り得た秘密情報や顧客情報などを不正に利用することによって、前の会社に営業上の損害を与えるような行為をいいます。
競業行為は、従業員が自ら競合する事業を起業することはもちろん、競合する他社に就職(転職)することも含みます。
また、広い意味では、元同僚や部下を勧誘して、引き抜く行為なども含まれます。
「職業選択の自由」と競業避止義務
競業避止義務を課すことは、同時に、退職する従業員のキャリアを奪うことでもあります。
そして、日本国憲法には、国民の権利として「職業選択の自由」が定められています。
「職業選択の自由」とは、国民が、自らが行う職業を自由に選択することができる権利をいいます。
つまり、競業避止義務を課す範囲を広げることは、逆に個人の権利を制限する(狭める)ことにつながるおそれがあることから、競業避止義務は、本来、必要最小限に留められるべき性質を有しています。
そこで、競業避止義務は、会社が営業秘密などを守る利益と、従業員の職業選択の自由との間で、両者の利益・不利益のバランスが整っているときに、初めて認められます。
.png)
競業避止義務の法律上の根拠
従業員が法律上、競業避止義務を負うかどうかについては、会社に在職中なのか、または退職した後なのかによって異なります。
在職中の競業避止義務
従業員が会社に在職しているときは、会社と従業員との間には、「労働契約」が存在します。
労働契約の内容には、従業員は会社に対して、損害を生じさせないよう、誠実に労働を提供する義務(これを「誠実義務」といいます)が含まれていると解されています(労働契約法第3条第4項)。
誠実義務は、合意や契約書の有無に関わらず、従業員が信義則上、当然に負うべき義務であると解されています。
そして、この(労働契約に基づく)誠実義務を根拠に、会社に在職している従業員は、もれなく、競業避止義務を負っているものと解され、それに違反することよって会社に損害を生じさせた場合には、損害を賠償する義務が生じる場合があり、また、社内規定によって懲戒処分(懲戒解雇など)の対象となる場合があります。
退職後の競業避止義務
競業避止義務は、労働契約に基づいて生じる義務であることから、従業員が退職した場合には、労働契約は解消され、それに伴って競業避止義務はなくなるのが原則です。
つまり、従業員は、退職後においては原則として競業避止義務を負いません。
会社が退職した従業員に対して、退職後も競業避止義務を負わせるためには、別に「契約上の根拠」が必要になります。
そこで、会社は、退職する従業員との間で、競業避止義務を定めた契約書や誓約書を締結することがあります。
しかし、前述のとおり、競業避止義務を負わせる場合、従業員の職業選択の自由を制限するに値するだけの合理的な範囲に収めることが求められます。
競業避止義務の範囲に「合理性がない」と判断される場合には、職業選択の自由を不当に制限するものとして、公序良俗違反となり、法律上、契約の効力が認められない場合があります(民法第90条)。
競業避止義務に関する契約・誓約内容の記載例
ご参考に、競業避止義務に関する契約書・誓約書の記載例をご紹介します。
貴社を退職した後において、貴社の業務に関わる重要な機密事項(顧客情報、取引情報、貴社製品の製造過程や価格等)にかかる情報について漏洩しません。
また、貴社を退職した後、2年間においては、理由の如何に関わらず、在職中に担当していた営業地域、及びその隣接する都道府県内の同業他社(支店、営業所を含む)に就職をすること、または同地域において貴社と同種の事業を起業することにより、貴社の顧客に対して営業活動を行いません。
競業避止義務違反に対する会社の対抗措置
従業員が競業避止義務に違反した場合に、会社がとりうる対抗措置としては、主に次の3つがあります。
【競業避止義務違反に対する措置】
- 競業行為の差し止め請求
- 損害賠償請求
- 退職金の全部または一部の不支給
①競業行為の差し止め請求
会社は、競業避止義務違反に基づいて、競業行為の差し止めを求めることができます(民法第414条)。
競業行為の差し止めは、裁判所に請求することによって行います。
ただし、競業行為の差し止めは、従業員の職業選択の自由を直接的に制限するものであることから、特に差し止めにかかる競業避止義務の有効性は、厳格に判断されることとなります(東京地方裁判所 平成7年10月16日決定)。
②損害賠償請求
競業避止義務違反があった場合には、通常の金銭債務などと同様に、債務(義務)の不履行があったものとして、損害賠償請求をすることができます(民法第415条)。
例えば、会社が顧客に提示した販売価格を、元従業員が競業会社に伝えたことに対する損害として、315万円の損害賠償請求が認められた裁判例があります(東京地方裁判所 平成15年4月25日判決)。
③退職金の全部または一部の不支給
競業避止義務は、退職時に課すことが多いため、その実効性を確保するために、違反があった場合には退職金を不支給とする旨を定める場合があります。
ただし、退職金は、在職中の功労に報いる性質も有するため、退職後の行為によって、退職金全額を支給しないことまで認められるかどうか、という問題は残ります。
裁判例では、競業避止義務違反があった場合には、退職金を半額にするという特約があったケースで、当該特約を有効と判断したものがあります(最高裁判所 昭和52年8月9日判決)。
競業避止義務の有効性に影響を与える判断要素
実際に競業避止義務が有効(合理性がある)と認められるかどうかは、裁判によってのみ決着がつくものです。
そして、これらの裁判は事案ごとの個別性が強いため、会社ごとの個別事情に応じて判断されるものです。
以下の6つの判断要素は、これまでの裁判例をもとに、結果の傾向を分析したもので、必ずしもすべての場合に当てはまるものではないことにご留意ください。
【競業避止義務の有効性に影響を与える6つの判断要素】
- 会社の守られるべき利益
- 従業員の在職中の地位
- 地域の限定範囲
- 競業を禁止する期間
- 禁止する行為の範囲
- 代償措置
①会社の守られるべき利益
会社が競業行為を禁止する目的(必要性)があるかどうか、言い換えると、競業行為を禁止することによって、会社に法的な保護に値するような、守られるべき利益があるかどうかが問題となります。
例えば、会社の営業上の秘密や、会社が独自に確立したノウハウや高度な技術を守る必要性がある場合には、正当な利益があるものとして認められやすい傾向にあります。
一方で、一般的な人脈や交渉術、業務上の視点、手法程度のノウハウであれば、正当な利益は認められない傾向があります(東京地方裁判所 平成24年1月13日判決)。
②従業員の在職中の地位
従業員の在職中の地位が、競業避止義務の有効性に影響を与える場合があります。
在職中、社内での地位が高い従業員や、機密性の高い情報に接する機会が多い業務に従事していた従業員の場合は、競業避止義務が有効と認められやすい傾向があります。
一方で、一般の従業員(役職がなく、一般的な業務に従事する従業員)になるほど、競業避止義務が無効となる可能性が高まるといえます。
ただし、これは形式的な職位だけで判断するのではなく、高い地位にある従業員を対象とした競業避止義務であっても、実際の業務において会社が守るべき秘密情報に接していなければ、有効とは認められないこともあります(東京地方裁判所 平成24年1月13日判決)。
③地域の限定範囲
就業する地域を広範囲にするほど、不当に従業員の権利を制限するものとして、競業避止義務が無効となる可能性は高まります。
④競業を禁止する期間
競業が禁止される期間を長くするほど、不当に従業員の権利を制限するものとして、競業避止義務が無効となる可能性は高まります。
裁判例をみると、退職後1年程度であれば、比較的有効と判断されるケースが多いといえます(大阪地方裁判所 平成21年10月23日決定)し、2年、3年と長くなるほど、有効と判断した裁判例を見つけることが難しくなる傾向があります。
⑤禁止する行為の範囲
抽象的・一般的な定め方は、有効とは認められない傾向があります。
単に「同業他社への転職を禁ずる」というよりも、できる限り具体的な業種や職種まで限定する方が望ましいといえます。
⑥代償措置
代償措置とは、従業員が競業を制限されることによって被るであろうとされる、経済的な不利益を補填するための措置をいいます。
従業員が競業を制限されることによって被る損害は、事案によって大きく異なるため、いくら支払えば問題ないというような基準はありません。
代償措置は、金銭によることが一般的です。
退職金を上乗せする方法や、あるいは在職中から手当などの形で支給する方法もあります。
例えば、退職後に2年間の競業避止義務を課す従業員に対して、在職中から特別に「機密保持手当」を支給していたことから、競業避止義務を有効と判断した裁判例があります(奈良地方裁判所 昭和45年10月23日判決)。
.png)
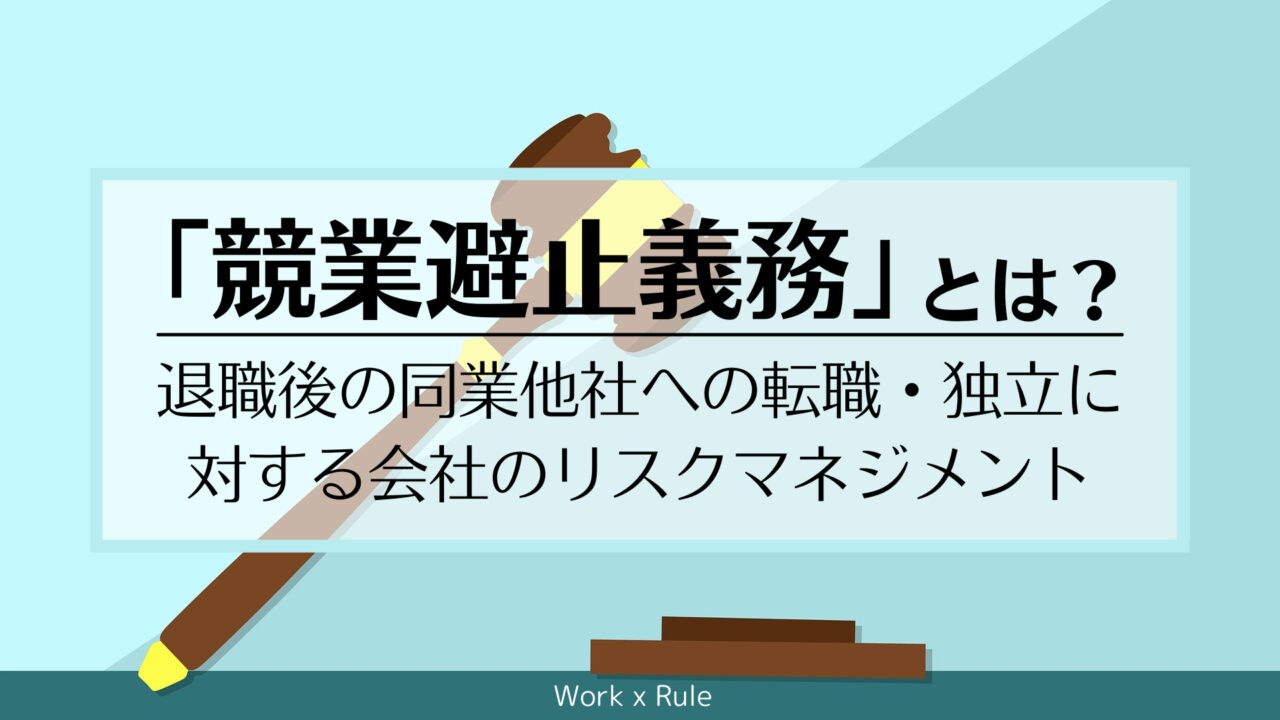

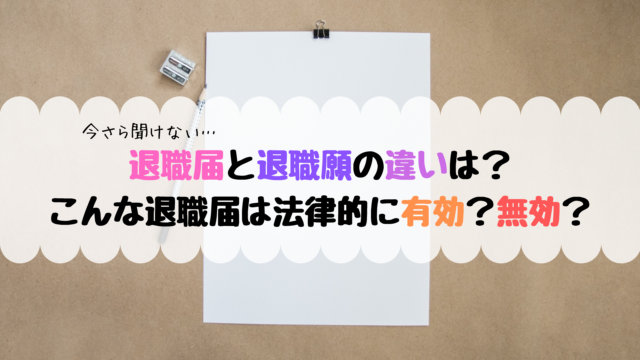
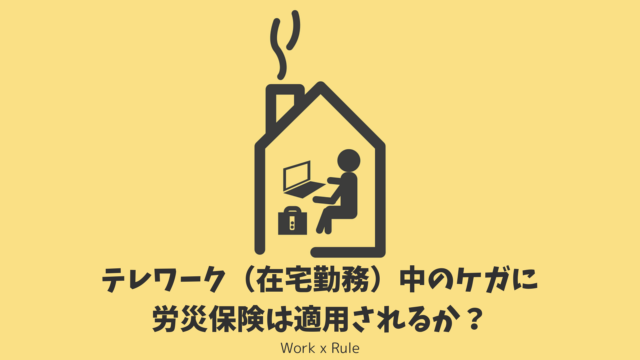


.png
)
.jpg)









