会社は、従業員との間で雇用契約を締結していますが、この雇用契約には、契約期間が定められていないもの(無期契約、典型例は正社員など)と、あらかじめ契約期間を定めているもの(有期契約、典型例はパート・契約社員など)とがあります。
そして、契約期間がある場合、その途中(満了前)であるにも関わらず、その後の事情の変化によって、会社が従業員を解雇する必要性が生じた場合や、逆に従業員が会社を退職したいと思い至るケースもあります。
しかし、一度は雇用契約が有効に成立している以上、会社と従業員がお互いに自由に解雇・退職できるものではなく、そこには法律上の規制が存在します。
そこで、今回は、雇用契約期間の途中(満了前)に、会社の側から従業員を「解雇」する場合と、従業員が自ら「退職」する場合とに分けて、それぞれどのような法律上の問題が生じるのか、解説します。
Contents
会社が契約期間の途中で従業員(パート・契約社員など)を解雇する場合
会社が、パートや契約社員など、契約期間の定めがある従業員を解雇する場合には、次の法律上の制限があります。
(契約期間中の解雇等)
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
この条文によると、会社は、「やむを得ない事由」がなければ、有期契約の従業員を解雇することができないとされています。
これは、逆に、会社は「やむを得ない事由」が存在しないにも関わらず、契約期間の途中で従業員を解雇すると、その解雇は法律上「無効」になる(違法であり、認められない)ことを意味します。
なお、労働契約法には罰則がありませんので、条文に違反すること自体に行政的なペナルティはありません。
ただし、解雇が無効になることによって、会社は従業員への損害賠償や、従業員を復職させるなどの措置をとる必要性が生じることがあります。
労働契約法第17条の「やむを得ない事由」とは?
それでは、「やむを得ない事由」とは、一体どのような事由を指すのでしょうか。
もともと、会社が従業員を解雇する場合には、「客観的に合理的な理由及び社会通念上相当である事情」が必要であるとされています。
これを「解雇権の濫用法理」といい、労働契約法の第16条に定められています。
この法理は、すべての雇用契約に適用される一般原則として存在しています。
そして、期間の定めがある有期の雇用契約については、期間の定めのない雇用契約(無期契約)の場合よりも、解雇の有効性について、狭く(厳しく)判断されることに留意が必要です(平成20年1月23日 基発第0123004号)。
「やむを得ない事由」については、条文の定めがないため、解釈によることとされています。
例えば、裁判例(仙台高等裁判所 平成24年1月25日判決)では、「やむを得ない事由」を、次のように示しています。
「やむを得ない事由」とは、(①)客観的に合理的な理由及び社会通念上相当である事情に加えて、(②)当該雇用を終了させざるを得ない特段の事情と解するのが相当である。
①の部分は、前述した「解雇権の濫用法理」を指します。
上記②では、①に加えて、さらに「特段の事情」があることまで求めているのですから、会社にとって、有期契約の従業員を解雇するハードルがいかに高いものであるかがお分かりいただけると思います。
この「特段の事情」がどのような事情であるのかは、決まった定義は存在しないため、事例ごとに個別の事情を踏まえながら判断されることになります。
労働契約法第17条の「やむを得ない事由」の具体例と裁判例
労働契約法第17条の「やむを得ない事由」の具体例
「やむを得ない事由」の判断については、事例ごとの個別性が強いものではありますが、これまでの裁判例などに照らすと、実際に「やむを得ない事由」に該当するのは、およそ次のような場合であると解されます。
【「やむを得ない事由」の具体例】
- 労働者が就労不能になったこと
- 労働者に重大な非違行為があったこと
- 雇用の継続を困難とするような経営難
「やむを得ない事由」があると判断された裁判例
上記の具体例②に関連して、大阪地方裁判所の平成27年5月29日判決では、具体的に以下の事由が「やむを得ない事由」に該当すると判断されました。
裁判所は、従業員が「業務上の指示命令に従わない」などの理由があるだけでなく、「雇用期間の中途で解雇しなければならない」というほどの解雇事由が認められるどうかを判断することが必要であると示しました。
この裁判例では、従業員の問題行動(上司への暴言・罵声など)が次第に激化していき、職場の秩序維持や業務遂行にさらなる悪影響を及していくという、具体的で差し迫った危険がありました。
個人的な見解ですが、職場内の混乱が現実に存在していて、さらにそれが今後増大していく危険性があり、早急に対処する必要性が高いものであったことが、契約期間の途中の解雇が有効になるひとつのポイントになったのではないかと考えます。
また、東京地方裁判所の平成25年1月31日判決では、即戦力として採用された証券アナリストの従業員について、期待された能力には遠くおよばない状況であったこと、採用を決定する際に重要となる事実を隠していたことが、契約期間の途中の解雇を有効とするほどの「特別で重大な事由」があると判断され、解雇を有効としました。
パート・契約社員の解雇予告(解雇通知)と解雇予告手当は必要?不要?
これまで解説した解雇の有効性とは別の問題として、実際に従業員を解雇する場合には、「解雇予告」の手続が必要になります。
解雇予告の内容は、契約期間の満了時であるか、途中であるかによって異なりますので、場合分けして説明します。
契約期間の満了によって、更新をせずに契約を終了する場合(雇い止め)
有期労働契約においては、契約期間が満了すれば、原則として、特段の手続を行わなくても、自動的に契約が終了することとなります。
しかし、契約の終了後、雇用契約を更新し、それが何度も繰り返されているようなケースにおいては、従業員にとっては次の契約が更新されることを期待するのが当然であり、このような状況下において、会社が期間満了で契約を更新しない(雇い止め)ことは、実質的には解雇のようにも捉えられる側面があります。
「雇止め」とは、定められた雇用期間が満了するときに、会社が次回の更新を拒絶することによって契約を終了させることをいいます。
「雇い止め」と「解雇」は、法律上は違うものですので、区別することが必要です。
そこで、会社が次に該当する有期労働契約の契約を更新しない場合には、30日前までに予告をしなければならないとされています(厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」)。
【雇い止めをする際の解雇予告】
- 3回以上契約が更新されている場合
- 1年を超えて継続勤務している場合
契約期間の途中に、契約を終了させる場合
会社が契約期間の途中で、一方的に従業員との契約を終了させることは、法律的にみて「解雇」に該当します。
そこで、この場合には、労働基準法第20条により、会社は解雇予告または解雇予告手当の支払が必要になります。
解雇予告とは、会社側が従業員を解雇しようとする場合、原則として、少なくとも(遅くとも)30日前までに解雇の予告をしなければならない決まりのことをいいます。
このとき、もし会社が30日前までに予告をしない場合には、会社側は30日に不足するだけの平均賃金を、解雇予告手当として従業員に支払わなければなりません。
従業員から、契約期間の途中で自主退職を申し出る場合
期間の定めのない(無期)の雇用契約の場合であれば、民法の定めによって、従業員は会社に対して14日前に退職の意思を伝えることにより、契約を終了させることができます(民法第627条第1項)。
このとき、退職理由や、退職の必要性について問われることはなく、いわば従業員の自由な意思で退職を申し出ることができます。
しかし、この民法の条文は、「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」を前提にしているため、契約期間をあらかじめ定めている場合には、適用されません。
そこで、有期労働契約のあるときは、次に紹介する民法第628条が適用されることとなります。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
ここでも、会社が従業員を解雇するときと同様、「やむを得ない事由」が必要とされています。
これも個別の事例に応じて判断するしかありませんが、例えば、家族の介護をするために、どうしても仕事を続けられないというような事情があれば、「やむを得ない事由」と認められる可能性が高いといえます。
他にも、明らかに会社側に非があるような場合、例えば、会社が従業員の生命・身体に危害を及ぼすような労働を命じた場合や、賃金の不払いなどの重大な問題が生じているような場合には、やむを得ない事由があると判断される可能性が高いでしょう。
しかし、有期契約の従業員から、「自己都合退職をしたい」という申し出があった場合に、会社が「やむを得ない事由に該当しない」ことをもって従業員に対抗して辞めさせないようにすることは、現実的にはあまり有効な対抗手段ではありません。
本人の意に反する労働を強制することは労働基準法第5条で禁止される「強制労働」に該当し得る違法行為であり、何よりやる気のない従業員を無理に働かせることの会社のメリットもないためです。
そこで、この場合に実際に問題になるのは、「従業員に過失がある場合の損害賠償請求」です。
問題は「過失」がどのような場合に認められるのかは程度問題ではありますが、例えば、急な退職によって会社に損害を与えることを知っていながら、何の引継ぎもせずに辞める場合などは、会社から損害賠償を請求されるリスクが高い退職であるといえるでしょう。
労働条件が契約内容と違う場合
労働基準法第15条では、雇用の際に会社から提示された労働条件(労働時間や賃金など)が、実際の労働条件と違う場合には、従業員に、即時にその雇用契約を解除することができることを認めています。
契約期間の初日から1年が経過している場合の特例
上記の民法の定めに関わらず、「契約期間の初日から1年」が経過した後であれば、「やむを得ない事由」がない状況で退職したとしても、従業員に損害賠償責任が発生することはありません。
この条文は、雇用契約に期間を定める場合には、最長で原則3年まで契約することが認められていますが(労働基準法第14条)、3年という長期にわたって労働者を拘束することは酷な面もあることから「契約期間の初日から1年」が経過すれば、従業員の意思で自由に退職することを認めるという趣旨で設けられた法律です。
まとめ
期間が定められている労働契約については、会社が解雇する場合も、従業員から自主退職をする場合も、法的な判断が難しいケースがあります。
労使共に安易な解雇・退職は避け、無用なトラブルを招かないためにも、判断に迷ったら弁護士などの専門家に相談することが重要です。
.png)

.png)
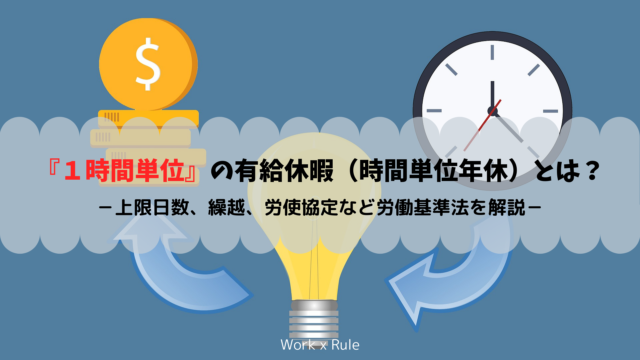




.png
)
.jpg)









