この裁判は、日本郵便株式会社に勤務する時給制の契約社員(以下、「時給制社員」といいます)3名が、手当などの労働条件について、正社員との間に「不合理な相違がある」として争ったものです。
そして、この裁判は「同一労働同一賃金」に関して、現時点では数少ない最高裁判所の判断として、世間的に大きく着目されるものとなりました。
同一労働同一賃金については、次の記事をご参考にしてください。


Contents
裁判所の判決の概要
この事件は、東京地方裁判所(第一審)、東京高等裁判所(第二審)および最高裁判所においてそれぞれ判決が出されました。
各判決内容を簡単にまとめると、正社員と時給制社員との労働条件の相違について、労働契約法第20条を適用し、「年末年始手当」、「住居手当」、「夏期冬期休暇」、「病気休暇」に関する相違は不合理なものであると判断しました。
一方、「外勤業務手当」、「早出勤務等手当」、「祝日給」、「夏期年末手当」、「夜間特別勤務手当」、「郵便外務・内務業務精通手当」に関する相違は不合理なものであるとはいえないと判断しました。
日本郵便における労働条件の違い
郵便業務を担当する正社員のうち「地域基幹職」および「旧一般職」は、郵便局において、配達業務などの外務事務、窓口業務などの内務事務について、幅広く従事することが想定されていました。
この正社員は、幅広い業務を経験させる目的や、局内の人員配置上の必要性から、郵便局を異にする異動だけでなく、同一局内でも、内務と外務との間の配置転換などが行われることがありました。
ただし、平成26年4月1日以降、新たな人事制度により「新一般職」が創設され、新一般職は、窓口営業、郵便内務、郵便外務、各種事務など標準的な業務に従事することとされており、役職層などが担当する管理業務を行うことは予定されていませんでした。
時給制社員は、外務事務または内務事務のうち、特定の定型業務に従事しており、これらの業務について幅広く従事することは想定されていませんでした(担当業務が変更されることは極めて例外的)。
正社員と時給制社員との間の労働条件の主な違いをまとめると、次のとおりです。
.png)
以下、手当ごとに各裁判所の判断を説明します。
年末年始勤務手当
この手当は、従業員が年末年始に勤務した場合に、一定額を支給するものです。
具体的には、12月29日から同月31日までは1日につき4,000円、1月1日から同月3日までは1日につき5,000円とされていました。
日本郵便では、正社員だけに支給され、時給制社員には支給されていませんでした。
裁判においては、第一審から最高裁判所まで、すべて「不合理である」と判断しました。
第一審(東京地方裁判所)
裁判所は、この手当の趣旨について、「多くの国民にとって休日である年末年始に働いたことの対価として支給するものであり、時給制社員に対してまったく支払わないということに「合理的な理由があるとはいえない」と判断しました。
ただし、手当の金額については、正社員と同額を支給するべきとまでは判断しませんでした。
その理由として、正社員は定年までの長期間にわたり、家族などと年末年始を過ごすことができず、長期雇用への動機付けをするために手当を支給している側面もあるため、この点については、時給制社員には当てはまらないと考えられるためです。
したがって、年末年始勤務手当については、正社員への支給額の約8割に相当する額を、従業員の損害として認めました。
第二審(東京高等裁判所)
裁判所は、第一審の判決を支持したうえで、正社員への支給額との差額の全額を、従業員の損害として認めました。
最高裁判所
最高裁判所は、年末年始勤務手当について、「年末年始勤務手当は、正社員が従事した業務の内容やその難度等に関わらず、所定の期間において実際に勤務したこと自体を支給要件とするものであり、その支給金額も、実際に勤務した時期と時間に応じて一律である」としたうえで、「上記のような年末年始勤務手当の性質や支給要件及び支給金額に照らせば、これを支給することとした趣旨は、郵便の業務を担当する時給制社員にも妥当するものである」としました。
結果として、「両者の間に年末年始勤務手当に係る労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができる」と判断しました。
.png)
住居手当
この手当は、住居費の負担を軽減するために支給するもので、家賃の額や住宅購入の際の借入額に応じて支給される手当です。
日本郵便では、正社員だけに支給され、時給制社員には支給されていませんでした。
第一審(東京地方裁判所)
裁判所は、この手当について、正社員のうち新一般職について、転居を伴う可能性のある人事異動が予定されていないにも関わらず住居手当が支給されていることとの関係から、時給制社員に対してまったく支払わないということに「合理的な理由があるとはいえない」と判断しました。
ただし、手当の金額については、正社員と同額を支給するべきとまでは判断しませんでした。
その理由として、住居手当には長期的な勤務に対する動機付けをするという意味もあることから、「時給制社員に対する住居手当(の金額)が正社員と同額でなければ不合理であるとまではいえない」として、住居手当については、正社員への支給額の約6割に相当する額を、従業員の損害として認めました。
第二審(東京高等裁判所)
比較の対象となる新一般職をみると、転居を伴う配置転換はないため、新一般職も時給制社員も住宅に要する費用は同じ程度であると判断し、新一般職に対しては住居手当を支給し、時給制社員には支給しないという労働条件の相違は、「不合理であると評価することができるものである」と判断しました。
さらに、第一審で損害額の6割を支給する理由となった「長期雇用者へのインセンティブ」「有為な人材確保」との日本郵便の主張を退け、住居手当の全額を損害として認定しました。
最高裁判所
最高裁判所では、住居手当についての判断はなされませんでした。
.png)
夏期冬期休暇
この休暇は、夏期と冬期にそれぞれ一定日数の休暇を与えるもので、在籍時期に応じ、暦日1日から3日まで有給休暇が与えられるものです。
正社員には夏期冬期休暇があり、時給制社員にはありませんでした。
第一審(東京地方裁判所)
裁判所は、お盆と年末年始を中核とする休暇は、国民的意識や慣習に基づくものであり、時給制社員に対してまったく与えないということには、「合理的な理由があるとはいえない」と判断しました。
ただし、夏期冬期休暇については、従業員(原告)が損害賠償請求をしていなかったため、具体的な損害額は認定されませんでした。
第二審(東京高等裁判所)
第二審においても、「その後国民的な習慣や意識などが変化し、夏期冬期休暇は、お盆や帰省のためとの趣旨が弱まり、休息や娯楽のための休暇の意味合いが増しているが、国民一般に広く受け入れられている慣習的な休暇との性格自体には変化はない」として、第一審の判断を踏襲しました。
第一審と同様に不合理と評価しつつも、損害の証明がないものとして、従業員(原告)の請求を棄却しました。
最高裁判所
最高裁判所は、第二審裁判所の判断は、不法行為に関する法令の解釈を誤っているものとして、従業員の損害を認定しました。
.png)
病気休暇
この休暇は、従業員の私傷病について、正社員には有給の休暇を少なくとも90日間与えるのに対し、時給制社員には無給の休暇を10日間としていたものです。
第一審(東京地方裁判所)
裁判所は、病気休暇が従業員の健康を保持するための制度であることに照らすと、どれだけ長期勤続をしたとしても、契約制社員には有給の病気休暇がまったく与えられないとすることには、「合理的な理由があるとはいえない」と判断しました。
ただし、病気休暇については、従業員(原告)が損害賠償請求をしていなかったため、具体的な損害額は認定されませんでした。
第二審(東京高等裁判所)
裁判所は、「長期雇用を前提とした正社員に対し日数の制限なく病気休暇を認めているのに対し、契約期間が限定され、短時間勤務の者も含まれる時給制社員に対し病気休暇を1年度において10日の範囲内で認めている労働条件の相違は、その日数の点においては、不合理であると評価することができるものとはいえない」としつつも、「しかし、正社員に対し私傷病の場合は有給(一定期間を超える期間については、基本給の月額及び調整手当を半減して支給)とし、時給制社員に対し私傷病の場合も無給としている労働条件の相違は、不合理であると評価することができる」と判断しました。
また、実際に病気で休まざるを得なかった分の賃金を、病気休暇の損害賠償として認めました。
最高裁判所
最高裁判所は、「正社員に対して有給の病気休暇が与えられているのは、正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、その生活保障を図り、私傷病の療養に専念させることを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的によるものと考えられる」としたうえで、「上記目的に照らせば、郵便の業務を担当する時給制社員についても、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば、私傷病による有給の病気休暇を与えることとした趣旨は妥当するというべきである」と判断しました。
そして、「第1審被告においては、時給制社員は、契約期間が6ヵ月以内とされており、第1審原告らのように有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど、相応に継続的な勤務が見込まれているといえる」ため、そうであるならば、「私傷病による病気休暇の日数につき相違を設けることはともかく、これを有給とするか無給とするかにつき労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができる」と判断しました。
.png)
夏期年末手当
この手当は、会社の財政状況を踏まえて、労使交渉によって金額が決定される手当であり、賞与の性質を有するものです。
正社員には支給され、時給制社員には同じく賞与の性質を有する「臨時手当」が支給されていました(金額の算定方法は異なる)。
第一審(東京地方裁判所)
裁判所は、次の理由から、この手当について、正社員と時給制社員との間の算定方法の相違について、「不合理とはいえない」と判断しました。
- 正社員と時給制社員の「職務の内容」ならびに「職務の内容および配置の変更の範囲には大きな、または一定の相違があること
- 同手当には将来の労働への意欲向上という意味合いもあり、長期雇用を前提とする正社員に対する支給を手厚くすることで優秀な人材の獲得、定着を図ることは人事上の施策として一定の合理性があること
- 時給制社員にも賞与的な性格のある臨時手当が支給されていること
第二審(東京高等裁判所)
第二審においても、夏期年末手当について、不合理であると評価することはできないと判断しました。
その理由として、「労働者の賃金に関する労働条件の在り方については、基本的には、団体交渉等による労使自治に委ねられるべき部分が大きいということもできるところ、夏期年末手当は、まさに、第1審被告の業績等を踏まえた労使交渉により支給内容が決定されるものである。そうすると、第1審原告ら主張の夏期年末手当の金額の相違を考慮しても、これを不合理であると評価することはできない」としました。
最高裁判所
最高裁判所では、夏期年末手当についての判断はなされませんでした。
.png)
.png)

.png)


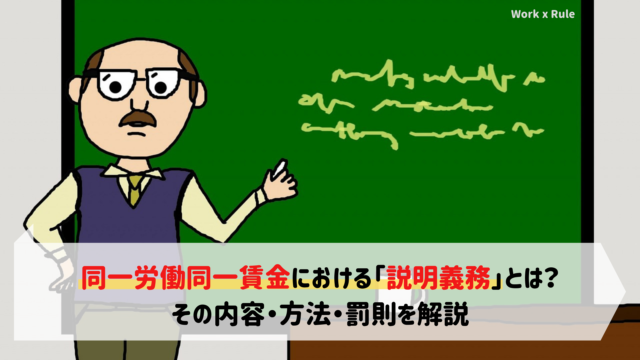


.png
)
.jpg)









