働き方改革法(2018年6月29日成立)では、残業時間の上限規制について、労働基準法の改正がありました。
働き方改革法の中でも、ひときわ実務への影響が大きい改正といえます。
残業時間の上限規制は、基本的な知識やこれまでの経緯を知らないと、内容を正しく理解できないおそれがあります。
そこで、まずは「入門編」として、残業時間の上限規制について、全体像を3つのポイントに絞って解説します。
.jpg)
Contents
1つめのポイント「残業時間に上限が設けられた」
まず結論をいうと、働き方改革法によって、残業時間について「何時間まで」という上限が設けられました。
なお、ここでは馴染みのある言葉として残業時間といいますが、正確には(法律では)「時間外労働」といいます。
働き方改革法ができるまでは、残業時間の上限は、「あるようでなかった」といえます。
以下、その理由をご説明します。
労働時間の基本原則
働き方改革法を理解するために、まずは労働時間の基本的な仕組みをご説明します。
まず、労働時間の大原則として、
「1日8時間ルール」と
「1週40時間ルール」があります。
これを「法定労働時間(法律で定められている、基本的な労働時間)」といい、労働基準法という法律の第32条に定められています。
簡単にいうと、基本的に、1日の労働時間は8時間以内に収まるようにしなさい、というルールです。
そのとおりです。
まずは、法定労働時間内に労働時間を収める努力が必要になる、ということです。
残業時間と36協定
多くの会社では、業務の必要上、1日8時間(または1週40時間)を超えて働く必要が生じます。
しかし、もし法定労働時間を超えて働く必要がある場合、つまり残業をする必要がある場合であっても、法律上、何も手続きをせずに、従業員にいきなり残業をしてもらうことはできません。
ここで、「36(さぶろく)協定」という手続きが必要になります。
36協定とは、簡単にいうと、従業員に「何時間までなら残業をしてもいいですよ」ということについて合意をしてもらうための手続です。
実務上は、36協定は、従業員の代表者に書面に押印してもらう形で、締結します。
その場合には、会社は、従業員の代表者に合意をしてもらわない限り、従業員に適法に残業をしてもらうことはできないということになります。
また、36協定には、残業の有無だけでなく、1日や1ヵ月単位などで、それぞれ「何時間までなら残業をしてもいいか」という上限の時間を協定しますので、残業時間はその定められた時間の範囲内であることが必要になります。
残業時間の上限
法律には、残業時間に関する上限は定められていませんでした。
しかし、法律とは別に、「労働時間の延長の限度に関する基準」というものが、存在していました。
この基準では、例えば1ヵ月の残業時間は45時間まで、1年では360時間まで…というように、期間ごとに残業時間の上限が定められていました。
しかし、この上限は、「基準」という名のとおり、法律で決まっていたものではなく、あくまでも行政(厚生労働大臣)が出した目安のような意味合いしかありませんでした。
法律で決まっていない、ということは、法律に縛られない(法的な拘束力がない)、つまり、極論をいうと、「守らなくても問題がない」上限でした。(あくまで法律的には、ということに注意してください。長時間の労働は、健康管理などの面では問題があります)。
ただし、36協定は行政(労働基準監督署)に提出する必要がありますので、基準に定めてある上限を超えた時間が記載された36協定を提出すると、窓口で労働基準監督官に注意や指導をされる(「行政指導」といいます)ということはありました。
しかし、くどいようですが、その指導を守らなくても、法律的には問題はなく、罰せられることもありませんでした。
従業員がどれだけ長い時間残業をしたとしても、それが36協定で合意された時間の範囲内である限り、法的には問題はありませんでした。
以上を理解していただければ、前述の「上限があるようでなかった」という意味も分かると思います。
働き方改革法と残業時間の上限規制
これまでの法律では、残業時間に上限はなく、36協定の手続さえきちんとしておけば、かなりの長時間労働をすることもできました。
しかし、健康管理の面ではやはり長時間労働は問題があり、過労死などの痛ましい事件が社会的に問題になったこと、また、時間を意識せず長時間働くことで、仕事の生産性が低くなっているのではないか、ということも問題視されていました。
そこで、働き方改革法では、これまでは単なる基準でしかなかった残業時間の上限規制を、法律レベルに格上げし、明確な上限を設けました。
これにより、今後は、すべての会社で同じように残業時間の上限規制を守っていく必要があります。
2つめのポイント「残業時間の上限には2段階ある」
残業時間の上限には、2つの段階があります。
1つめの段階
残業時間の上限について、1つめの段階は、残業時間の上限は「1ヵ月に45時間まで」というものです。
他にも基準がありますが、ここでは入門編なので、割愛します。
まずは、残業時間の上限は、1ヵ月あたりの残業時間が45時間に達するまでがボーダーラインだと理解してください。
例えば、1ヵ月の営業日数が22日(週休2日)程度だとすると、1日あたりの残業時間は平均して約2時間程度までというイメージです。
実際には、仕事をしていると、急なトラブルがあるなど、どうしても残業時間が多くなる時期が生じてしまうことがあり得ます。
そこで登場するのが2つめの段階です。
2つめの段階
2つめの段階は、急なトラブルなどの特別な事情がある場合には、45時間を超えてさらに残業をすることができるというものです。
ここでも、上限の時間が決められています。
それは、「特別な事情がある場合に限って、残業時間は1ヵ月に100時間を上限とする」というものです。
正確にいうと、「100時間未満」ですので、ちょうど100時間の残業をするとアウトです。
ただし、これは当たり前に認められるものではなく、「もし特別な場合には、何時間を上限として残業することがあります」という内容を36協定に記載したうえで、従業員の代表者に合意をしてもらわなければいけません。
この合意の内容を、「特別条項」と呼びます。
そして、この特別条項には、「どんな理由のときに、何時間まで残業する」ということをきっちりと明記しなければなりません。
ただし、この理由は、単に忙しいから、人手が足りないからなどという理由では足りず、予期し得ないトラブルなど、「よほどの特別な事情」がなければいけないというイメージをもっておいてください。
「残業時間が1ヵ月で100時間…かなり多いですよね。従業員の健康面は大丈夫ですか?」
もちろん毎月100時間の残業をさせてしまうようなことになると、従業員の健康面に問題があります。
そこで、特別条項は無制限に使えないように、法律でいくつかの歯止めをかけています。
働き方改革法では、100時間という上限の他にも、歯止めとなるルールをいくつか設けることによって、かなり制限をかけています。
実際には、100時間まで残業をさせることができるのは、かなり特殊なケースに限られるといえるでしょう。
まずは、この入門編では、1ヵ月という期間について、残業時間の上限が「45時間」と「100時間(特別条項)」の2段階ある、ということを理解していただき、特別条項にはいくつかの歯止めとなるルールがあるということだけ知っていただければ十分かと思います。
.jpg)
3つめのポイント「法律を守らないと罰則がある」
働き方改革法では、法律を守らない場合の罰則が設けられました。
罰則があるということは、この法律には強制力がある、ということです。
罰則の内容は、「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」というものです。
まとめ
働き方改革法により、会社は、残業時間の上限をきちんと理解したうえで36協定を適法に締結し、適切に従業員の労務管理をしなければ罰則があるということになります。
しかも、残業時間の上限は、とても規制の内容が細かいため、まずはその内容を正しく理解することが、正しい運用をするために重要になります。
残業時間の上限規制について、さらに細かい法律の内容については、機会を改めて解説していきたいと思います。
.png)

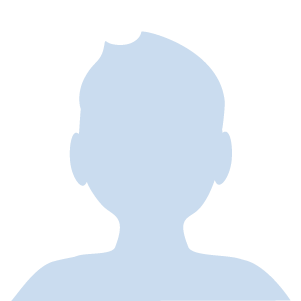





.png
)
.jpg)









