労働基準法では、休憩時間の与え方について定められており、単に「何時間働いたら何分休憩させるか」という点だけでなく、「どのように休憩させるか」という点についても注意が必要です。
この記事では、休憩時間に関する法律の内容について、その定義、与えるべき時間、与え方の留意点など、労働基準法を中心に詳しく解説します。
Contents
労働基準法上の休憩時間の定義
「休憩時間」とは法律上、労働から離れることを権利として保障されている時間をいいます(昭和22年9月13日 発基17号)。
労働から離れることが保障されていない場合の例としては、従業員が昼の休憩時間に、電話番や来客対応するためにデスクで待機している場合などがあります。
この場合、「電話をとる」「来客対応する」という仕事のために、その従業員はデスクから離れることができないため、このような時間は仕事に拘束されており、法律上の休憩時間として扱われません。
休憩時間の与え方(6時間・8時間ルール)
会社が従業員に対して与えなければならない休憩時間の長さは、労働基準法によって定められています(労働基準法第34条第1項)。
休憩時間は、労働時間の長さに応じて、次のとおり定められています。
| 労働時間の長さ | 休憩時間の長さ |
| 6時間以内 | 与えなくてもよい |
| 6時間超 8時間以内 | 45分以上 |
| 8時間超 | 60分以上 |
ポイントは、労働時間が6時間「超」になって、初めて休憩時間を与える必要が生じる点です。
つまり、労働時間が6時間「ちょうど」であれば、休憩時間は「与えなくてもよい」ことになります。
そして、労働時間が6時間を1分でも超えた時点で、会社は初めて45分以上の休憩時間を与える必要が生じることとなります。
この理屈は労働時間が8時間の場合でも同じであり、労働時間が8時間ちょうどまでは休憩時間は45分以上で足り、8時間を1分でも超えた時点で、会社は60分以上の休憩時間を与える必要が生じることとなります。
.png)
そこで、例えば、「中抜け休憩」といった、「4時間労働→3時間休憩→4時間労働」というような働き方も可能です。
この場合、拘束時間は長くなるものの、労働時間はあくまで8時間となります。
なお、休憩時間に関する法律は、雇用形態を問わず等しく適用されます。
したがって、正社員、アルバイト、パートなどの雇用形態に関係なく、会社は従業員の労働時間に応じた休憩時間を与えなければなりません。
休憩時間の与え方に関する3つのルール(原則)
休憩時間の与え方に関する3つの原則
休憩時間については、その与え方について、労働基準法によって3つの原則が定められています。
【休憩時間に関する3つの原則】
- 途中付与の原則
- 一斉付与の原則
- 自由利用の原則
休憩時間の途中付与の原則
労働基準法により、休憩時間は、労働時間の途中に与えなければならないことが定められています(労働基準法第34条第1項)
したがって、休憩時間を最初(始業前)または最後(終業後)に与えることは認められません。
.png)
休憩時間の一斉付与の原則
休憩時間は、その事業場の従業員について、一斉に与えなければならないとする原則をいいます(労働基準法第34条第2項)。
しかし、実際には、会社の組織や業務内容などの事情によって、全員を一斉に休憩させることができない場合があります。
そこで、次の場合には例外的に、一斉に休憩時間を与えないことが認められています。
【一斉付与の原則の例外】
- 労使協定を締結した場合
- 法律による特例が適用される業種である場合
①労使協定を締結した場合
労使協定とは簡単にいうと、会社と従業員との間で、労働条件について取り決めることをいいます。
労使協定では、次の内容を定めておく必要があります(労働基準法施行規則第15条)。
【労使協定の内容】
- 一斉に休憩を与えないこととする従業員の範囲(部署・業務内容など)
- その従業員に対する休憩時間の与え方
参考に労使協定の記載例をご紹介します。
.png)
②法律による特例が適用される業種である場合
一斉付与の原則には、業種によって法律で特例が認められる場合があります(労働基準法施行規則第31条)。
以下の業種に該当する場合には、①の労使協定を締結することなく、休憩時間を一斉に与える必要がなく、業務の繁閑に応じて交代で休憩させることができます。
- 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業(別表第一の四)
- 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業(同表八)
- 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業(同表九)
- 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業(同表十)
- 郵便、信書便又は電気通信の事業(同表十一)
- 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業(同表十三)
- 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業(同表十四)
- 官公署の事業
休憩時間の自由利用の原則
休憩時間は、従業員に自由に利用させなければならないとする原則です(労働基準法第34条第3項)。
これは、休憩時間の定義にもあった「労働から離れることを保障」することを裏付けるための原則といえます。
ただし、以下の業種については、自由利用の原則が適用されません(労働基準法施行規則第34条)。
- 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
- 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
- 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者
例えば、従業員が休憩時間中に外出することについて、所属長の許可を受けさせるとしても、職場内で自由に休憩することを保障している限り、必ずしも違法になるものではありません(昭和23年10月30日基発1575号)。しかし、会社はどのような状況であっても必ず自由利用をさせなければならないものではなく、職場の規律を保持するために必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差支えありません(昭和22年9月13日基発17号)。
労働基準法の基準を上回る休憩時間
労働基準法の基準を上回る休憩時間については、上記の3つの原則は適用されません。
例えば、法律上60分の休憩時間を与えるべきところ、会社が独自に90分の休憩時間を与えているような場合には、法律を上回る30分については、必ずしも途中に与えたり、一斉に与える必要はありません。
残業(時間外労働)をした場合の休憩時間
従業員が残業をした場合、それによって会社が与えるべき休憩時間が変わるケースがあります。
例えば以下の図の例では、所定労働時間が9時から17時45分であり、労働時間が8時間ちょうどであることから、法律上与えるべき労働時間は45分です。
.png)
しかし、従業員が残業をした場合には、労働時間が8時間を超えることになるため、会社は追加で15分の休憩時間を与える必要が生じます。
同様の事例として、もともと所定労働時間が6時間ちょうど(休憩時間は不要)であった場合に、残業によって6時間を超えることとなった場合に、追加で45分の休憩時間を与えなければならないこととなります。
休憩時間の分割が適法・違法となるケース
休憩時間を分割して与えてはならない、とする法律の規制はありません。
したがって、例えば60分の休憩時間を4分割して、15分ずつ休憩時間を与えることとしても、それをもって違法になることはありません。
.png)
ただし、だからといって「60分の休憩時間を12分割して、5分ずつ休憩時間を与えるのはどうか」といわれると、問題があると考えます。
休憩時間の趣旨は、心身を休めて疲労を回復させることにありますから、5分程度の休憩で果たしてそれが可能かという点で疑問ですし、昼休憩においては少なくとも30分程度は昼食をとることができる休憩時間を確保することが望ましいと考えます。
なお、前述のとおり、休憩時間を分割したからといって、労働時間の最初または最後に与えることはできない点に留意してください。
職場の休憩所・休憩室の設置に関するルール
職場に休憩室など、従業員が休憩するための場所の確保が必要かという点については、労働安全衛生規則第613条によれば、「事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。」と定められているのみで、あくまでも会社の努力義務という位置づけにあります。
これと混同しやすいものとして、休養室があります。
労働安全衛生法618条では、「事業者は、常時50以上又は常時女性30以上の労働者を使用するときは、労働者が、が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」と定めています。
上記の人数要件を満たす場合、会社は体調不良の従業員が横になって休めるスペースを設置する義務があります。
罰則
会社が休憩時間に関する法令に違反した場合には、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑罰が科せられることがあります(労働基準法119条第1号)。
.png)

.png)
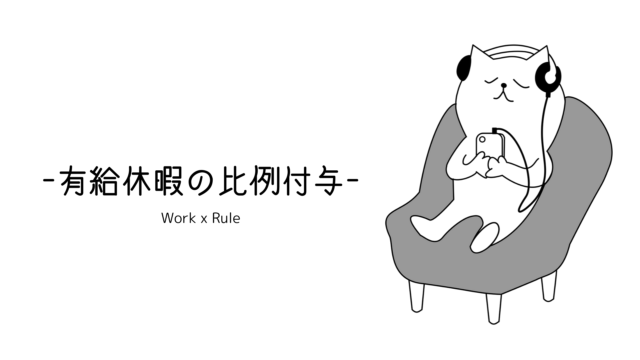




.png
)
.jpg)









