会社が行う労務管理において、従業員の労働時間を適正に把握することは、もっとも基本的かつ重要です。
しかし、営業職など会社の外で働く従業員については、厳密に労働時間を把握することが困難な場合があるため、労働基準法では「事業場外労働のみなし労働時間制」という制度が設けられています。
事業場外労働のみなし労働時間制は、正しく運用されていないケースも散見され、そのような場合、会社にとって思わぬ労務リスクが生じる場合があります。
そこで、今回は、事業場外労働のみなし労働時間制について、その制度の内容、要件、導入手続、運用など、基本的な事項を解説するとともに、運用時に問題となりやすい「内勤」の取り扱いについても事例を交えながら説明します。
Contents
「事業場外労働のみなし労働時間制」とは?
「事業場外労働のみなし労働時間制」とは、従業員の労働時間の算定について、特別な取り扱いをする制度をいい、労働基準法第38条の2に定められています。
会社は本来、従業員の労働時間を正確に把握する義務があり、労働時間の把握は、労務管理の中で最も基本的かつ重要な事項のひとつです。
しかし、外回り営業職(保険の勧誘、製品やサービスの営業販売)や新聞記者による記事の取材など、従業員が会社の外(事業場外)で仕事をする場合には、会社の目が届かず、労働時間の正確な把握が難しくなる場合があります。
そこで、このような場合、例外的に、一定の要件を満たすことにより、会社の労働時間の算定義務を免除し、事業場外での労働時間については、あらかじめ労使で取り決めた時間働いたものとみなす、という労務管理が認められています。
事業場外労働のみなし労働時間制は、1987年の労働基準法の改正によって創設されました。
厚生労働省の「平成30年就労条件総合調査」によると、有効回答3,697社のうち、事業場外労働のみなし労働時間制を採用している会社は、全体の14.3%でした。
事業場外労働のみなし労働時間制の対象となる業務
従業員が会社の外で働くからといって、どのような業務内容であっても、事業場外労働のみなし労働時間制を適用することができることにはなりません。
事業場外労働のみなし労働時間制を適用するためには、従業員が事業場外で行う業務が、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 事業場外で業務に従事すること
- 使用者の具体的な指揮監督が及ばないこと
- 労働時間の算定が困難であること
上記のうち、特に②の要件が重要です。
「使用者の具体的な指揮監督」とは、例えば、「何時に取引先Aに出張し、そこで業務Bを行った後、取引先Cに移動し…」というような、上司からの具体的な指示命令を受けている場合をいいます。
このように、もし、「使用者の具体的な指揮監督ができる」という状況なのであれば、会社は、その業務について、具体的な労働時間を把握できることができるため、労働時間をみなしてしまうことはできません。
事業場外労働のみなし労働時間制を適用する場合には、従業員が外出先でどのような時間配分で営業活動などの業務を展開するのか、従業員の裁量に任せている状況におくことが重要になります。
稀に、「営業職=みなし労働時間制の対象となる」というような、安易な認識で労務管理がなされているケースがあります。
事業場外労働のみなし労働時間制は、あくまで例外的な位置づけにあって、厳しい要件のもと適用されるべきものであることに注意が必要です。
事業場外労働のみなし労働時間制の対象とならない業務
適用要件について、さらに踏み込んだ解釈として、労働基準監督署の通達(昭和63年1月1日基発第1号)では、次のような場合には、使用者の指揮監督が及んでいる(=事業場外労働のみなし労働時間制は適用できない)ものと解釈することとしています。
- 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をするものがいる場合
- 無線やポケットベルなどによって、随時使用者の指示を受けながら事業場外で労働している場合
- 事業場において、訪問先、帰社時刻など当日の業務の具体的な指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業務に従事し、事業場に戻る場合
無線やポケットベルという言葉は、通達が出された昭和63年当時の状況が反映されています。
現代では、携帯電話の貸与やスマートフォンのGPS機能などにより、従業員の状況を常に監視することが可能になりました。
そうすると、現代では、使用者が労働時間を把握できない場合などあり得ないのではないか、との疑問も生じます。
この疑問に対しては、もはや現代社会においては、この制度を利用すること自体が難しい、という見解もあります。
しかし、一方で、会社側から指示をしようと思えば、いつでもできる状況にはあるが、従業員が、貸与された携帯電話などを用いて、常に会社から指示を受けていると評価できるくらいに密に連絡を取り合っているというような例外的な場合でない限り、問題はないとする見解もあります。
なお、裁判例の中には、「携帯電話等の情報通信機器の活用や労働者からの詳細な自己申告の方法によれば労働時間の算定が可能」であったとしても、業務に関する労働者の裁量の大きさや、使用者による指揮命令が及んでいないと認められる各事情から、事業場外労働のみなし労働時間制の適用を肯定したものがあります(「ナック事件」東京高等裁判所平成30年6月21日判決)。
いずれにせよ、制度を適正に運用するためには、会社から従業員に対する指示・命令や、従業員からの報告など、外勤時の連絡をできる限り少なくする工夫が求められます。
労働時間の算定方法(みなし時間の決め方)
 事業場外労働のみなし労働時間制を適用する場合、具体的に、どのように労働時間をみなすことになるのかを説明します。
事業場外労働のみなし労働時間制を適用する場合、具体的に、どのように労働時間をみなすことになるのかを説明します。
事業場外労働のみなし労働時間制においては、次のいずれかの時間によって、労働時間を算定する(みなす)こととなります。
事業場外労働のみなし労働時間制の下では、従業員の実際の労働時間に関わらず、みなした時間働いたものと仮定して、労務管理を行うこととなります。
【事業場外労働のみなし労働時間の算定方法】
- 所定労働時間
- 通常必要時間
①所定労働時間
「所定労働時間」とは、1日の原則的な労働時間であり、始業時刻から終業時刻まで働いた場合の労働時間をいいます。
所定労働時間は、一般的には会社の就業規則や雇用契約書などに記載されています。
例えば、ある会社の就業規則で、始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩時間が1時間と定められていれば、その会社の所定労働時間は「8時間」になります。
②通常必要時間
従業員が、事業場の外で行う仕事の量によっては、労働時間が所定労働時間を超える場合があります。
そこで、事業場外の業務を遂行するための時間が、日常的に所定労働時間を超える場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間(通常必要時間)働いたものとみなすことができます。
通常必要時間は、事業場外で実際に必要とされた労働時間を平均した時間をもとに設定します。
例えば、所定労働時間が8時間の会社で、事業場外で行う業務が、平均的にみて10時間かかるものであれば、みなし労働時間を10時間とする必要があります。
通常必要時間が、業務の種類や時期(繁忙期、閑散期)、地域などによって異なる場合には、それぞれ別の時間を定めることもできます。
また、いったん定めた通常必要時間は、その後変えてはならないものではなく、適宜そのときの状況(忙しさなど)に応じて見直されるべきであると考えます。
事業場外労働のみなし労働時間制の適用手続
会社がはじめて事業場外労働のみなし労働時間制を導入する場合の手続は、みなし労働時間をどのように設定するかによって、次のいずれかの手続が必要です。
- 「みなし労働時間≦所定労働時間」のとき…就業規則に定める
- 「みなし労働時間>所定労働時間」のとき…労使協定を締結する
①の場合は、就業規則において、事業場外労働のみなし労働時間制について定めることとなります。
②の場合は、前述の「通常必要時間」を労使協定で締結する必要があります。
さらに、通常必要時間が法定労働時間を上回る場合には、その労使協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。
事業場「内」の業務(いわゆる「内勤」)がある場合の取り扱い
事業場外労働のみなし労働時間制を採用する場合に、運用上問題となりやすいのが、従業員が事業場内で働いた時間(内勤)の取り扱いです。
事業場外労働のみなし労働時間制は、その名のとおり、会社の「外」で働く時間の労働時間をどう算定するか、という問題を前提とした制度です。
しかし、外回りの営業職など、仕事の大部分が事業場外で行われる職種であっても、営業資料の作成や社内会議など、事業場「内」で仕事をする必要性が生じる場合があります。
そこで、この事業場内で行われた仕事の労働時間を、どのように取り扱うのかが問題になります。
内勤があった場合の労働時間の算定方法
結論をいいますと、いわゆる内勤があった場合には、その「実労働時間を把握する」必要があり、内勤時間を「みなす」ということはできません。
なぜなら、事業場外労働のみなし労働時間制は、事業場外で働くからこそ、会社の目が行き届かないために、労働時間を算定することができず、例外的に労働時間をみなすことを認める制度であって、内勤のように会社の中で行う労働時間までみなしてしまうことは、制度の趣旨に沿わないためです。
1日のすべてを内勤する場合
事業場外労働のみなし労働時間制を適用する余地はないため、単純に内勤した時間をそのまま労働時間としてカウントします。
1日の中で、外勤と内勤とが混在する場合
1日の中で外勤と内勤が混在する場合の労働時間の算定は、次のようになります。
- 1日の労働時間=事業場外におけるみなし労働時間+事業場内の実労働時間
- ①の時間が所定労働時間を下回る場合には、所定労働時間
以下、具体例をもとにご説明します。
事例(内勤と外勤が混在する場合)
【前提】
- 所定労働時間…8時間(午前9時~午後6時、休憩1時間)
- みなし労働時間(通常必要時間)…3時間
- 午前9時から3時間内勤をして、その後、事業場外で働き、直帰した
この事例では、内勤時間である3時間は実労働時間で把握するため、労働時間は3時間となります。
次に、事業場外で働いた時間については、みなし労働時間が適用されることにより、実労働時間に関わらず、労働時間は3時間となります。
これらを合計すると(3+3)、6時間になります。
.png) この事例では、所定労働時間が8時間であり、6時間よりも長いため、上記の②が適用されることにより、この日の1日の労働時間は「8時間」として算定することとなります。
この事例では、所定労働時間が8時間であり、6時間よりも長いため、上記の②が適用されることにより、この日の1日の労働時間は「8時間」として算定することとなります。
この事例で、もし、みなし労働時間(通常必要時間)を「6時間」と定めていた場合はどうでしょうか。
この場合には、内勤時間3時間と、通常必要時間6時間を合計すると、9時間になります。
そこで、この事例では、上記の①が適用されることにより、この日の1日の労働時間は「9時間」として算定することとなります。
残業代(割増賃金)休憩、休日、深夜業との関係
事業場外労働のみなし労働時間制は、あくまで労働時間の算定に関する例外であって、法定労働時間や割増賃金(残業代)については、例外は認められません。
したがって、例えば、みなし労働時間が8時間を超える場合には、原則として割増賃金の支払が必要となります。
また、事業場外労働のみなし労働時間制についても、休憩、休日、深夜業に関する規定は適用されるため、会社は従業員に対して休憩、休日を与えなければならず、また、休日労働、深夜業に従事させた場合には、割増賃金の支払が必要になります。
事業場外労働のみなし労働時間制の就業規則・雇用契約書の規定例
事業場外労働のみなし労働時間制を就業規則に定める場合の規定例をご紹介します。
【就業規則の例】
第〇条 従業員が、労働時間の全部または一部について、事業場外で労働した場合であって、労働時間を算定することが困難な業務に従事したときは、就業規則〇条に規定する所定労働時間を労働したものとみなす。
2 前項の事業場外の業務を遂行するために、所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には、その業務については通常必要とされる時間労働したものとみなす。
3 労働基準法第38条の2第2項に基づく労使協定が締結された場合には、前項の事業場外業務の遂行に通常必要とされる時間は、労使協定で定める時間とする。
事業場外労働のみなし労働時間制に関する裁判例
阪急トラベルサポート割増賃金請求事件(最高裁判所判決平成26年1月24日)
この判決は、事業場外労働のみなし労働時間制に関する唯一の最高裁判所の判決であり、運用において参考とするべき有名な判例です。
結論としては、裁判所は事業場労働のみなし労働時間制を否定しました。
その上で、法定労働時間を超過する時間に対する割増賃金などを遡って支払うなどといった対応が必要になります。
この事例では、会社は、海外旅行の添乗員に対し、国際電話用の携帯電話を貸与し、常にその電源を入れておくものとした上、添乗日報を作成して提出することも指示していました。
この添乗員について、事業場外労働のみなし労働時間制を適用できるのかどうかが争われました。
裁判所は、次の理由から、添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法第38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当であると判断しました。
- 添乗業務は、旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られているものということができる。
- 添乗日報には、行程に沿って最初の出発地、運送機関の発着地、観光地等の目的地、最終の到着地及びそれらに係る出発時刻、到着時刻等を正確かつ詳細に記載し、各施設の状況や食事の内容等も記載するものとされており、添乗日報の記載内容は、添乗員の旅程の管理等の状況を具体的に把握することができるものとなっている。
まとめ
今や外回りの営業職について、スマートフォンによる位置の把握や、勤怠システムの入ったタブレットやパソコンの貸与など、従業員の労働状況を会社が把握することは容易になりつつあります。
その中で、事業場外労働のみなし労働時間制を運用する場合には、従業員に対して大幅な裁量をもたせるとともに、直行直帰など、より柔軟な働き方を認める必要性があります。
このことは、昨今の働き方改革推進の波にも沿うものであり、労働時間の長短よりも「成果」を軸とした労務管理を推進していくことにもつながると考えます。
従業員の働きやすさと、会社の成果とが相乗的に向上することのできるよう、事業場外労働のみなし労働時間制を上手に活用していただければと思います。
.png)

.png)

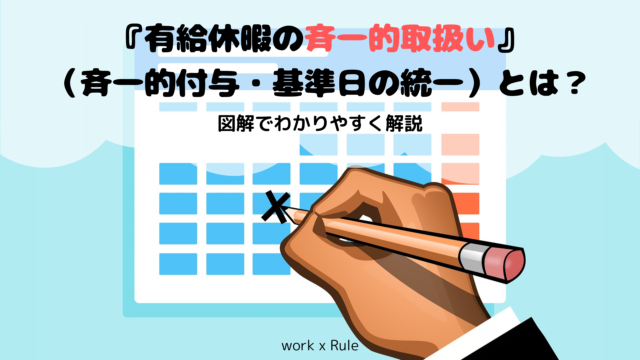



.png
)
.jpg)









