今、日本では、高齢化が世界に類を見ない速さで進行しています。
2015年の国勢調査によれば、65歳以上人口は約3,346万人で、総人口に占める割合は26.6%に上っており、日本はすでに4人に1人が高齢者という「超高齢社会」になっています。
それに伴い、年金の支給開始年齢の引上げや、同一労働同一賃金の問題などもあり、定年を迎えた高年齢の従業員についてどのように労務管理していくべきなのか、頭を悩ませている会社も多いことと思います。
そこで、今回は、従業員の「定年と再雇用」に関する労務管理について、法律と賃金という2つの視点から解説します。
なお、記事の分量が多くなりますので、Part1では法律編、Part2では賃金編と、2回に分けて掲載します。

Part1 法律編
定年に関する法律
定年の年齢については、「高年齢者雇用安定法」という法律で、下限(これ以上、下回ってはいけない年齢)が定められています。
高年齢者雇用安定法 第8条
事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は60歳を下回ることができない。
逆にいうと、上限については法律の定めがありませんので、例えば定年を80歳と定めたとしても、問題ありません。
定年は、必ずしも決めておく必要はありません。
ただし、定年を決めていない場合(就業規則や雇用契約書などに定年の定めがない場合)には、「定年がない会社」であると判断されることに注意が必要です。
なお、以下の統計によると、多くの会社が定年を設けているようです。
(参考)平成29年就労条件総合調査(平成29年12月27日公表)
定年を定めている会社の割合…95.5%
定年を定めていない会社の割合…4.5%
60歳を下回る定年(例えば55歳を定年とする、など)を設けたとしても、その制度は無効となり、定年の定めがない(=定年がない)ものとみなされますので注意が必要です。
「高年齢者の雇用確保措置」とは
高年齢者雇用安定法により、65歳未満の定年を定めている会社は、次の①から③に定める高年齢者雇用確保措置のうち、いずれかを選択して実施する必要があります(第9条)。
①定年の引上げ
→定年の年齢を65歳まで引き上げること
②継続雇用制度の導入
→定年を迎えた高年齢者が希望するときは、その高年齢者を定年後も引き続いて雇用する制度を導入すること
③定年の定めの廃止
→定年をなくすこと
さらに、②の継続雇用制度には、2つの選択肢があります。
②-A 勤務延長制度
60歳以降も職務内容や賃金などの労働条件を変更せずに、65歳までは今までと同じ待遇で仕事に就くことをいいます。
②-B 再雇用制度
いったん定年退職した後、新たな内容の雇用契約を結び、嘱託社員など今までとは異なる待遇で仕事に就くことをいいます。
平成29年就労条件総合調査(平成29年12月27日公表)によると、②の継続雇用制度を導入している会社が92.9%を占めており、多数といえます。
また、そのうち②-A勤務延長制度のみの会社は9.0%、②-B再雇用制度のみの会社は72.2%、両方の制度を併用している会社は11.8%でした。
世間的には、再雇用制度を導入している会社が多いようですね。
退職日の設定

退職日の決め方には、以下の4つのパターンがあります(例として、60歳が定年の年齢である場合)。
①60歳の誕生日に達した日
②60歳の誕生月の末日
③60歳の誕生月に属する賃金計算の締め日
④60歳の誕生日以降の最初の3月31日
なお、①の「誕生日に達した日」は、誕生日当日ではない点に注意が必要です。
法律上の60歳に達した日とは、60歳の「誕生日の前日」をいいます。
したがって、4月1日生まれの方の場合、定年による退職日は、その前日の3月31日になります。
就業規則の規定例
前述のとおり、定年に関する制度は、就業規則などにきちんと定めておく必要がありますので、参考に規定例をご紹介します。
以下、厚生労働省モデル就業規則(2018年1月版)を元に編集
【例1】定年を満65歳とする例
第●条 従業員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とします。
【例2】定年を満60歳とし、その後、希望者を継続雇用する例
第●条 従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とします。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由または退職事由に該当しない従業員については、満65歳までこれを継続雇用します。
再雇用に伴う職務内容の変更
一般的には、定年に伴い、職種や賃金を中心として、労働条件が変更されることが多いと思います。
法律では、「継続雇用すること」までが義務とされており、「同じ条件で雇用すること」までは求めていません。
そして、再雇用の場合には、定年によりこれまでの契約がいったんリセットされ、新たな契約が結ばれるのですから、会社から提示する労働条件も、これまでの実績に縛られる必要はありません。
なお、(独)労働政策研究・研修機構による高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)(平成28年6月30日公表)によると、60代前半層の継続雇用者の仕事内容に関する状況は以下のとおりです。
定年前(60歳頃)とまったく同じ仕事…39.5%
定年前(60歳頃)と同じ仕事であるが、責任の重さが変わる…40.5%
職務内容の大幅な変更
ただし、職務内容をあまりにも大きく変更することについては、以下の判例がありますので注意が必要です。
トヨタ自動車事件(名古屋地裁平成28年9月28日判決)
会社が授業員に対し、定年後、パートタイマーとしての再雇用を以下の条件で提示したところ、②の業務内容については高年齢者雇用安定法の趣旨に反して違法であるとされました。
①年収が約87%減少する
②業務内容を事務職から清掃等の業務に変更する
つまり、定年後、再雇用に伴って、「職務内容を大幅に変更する」ことについては、ある程度のリスクが伴うといえます。
有給休暇の注意点
再雇用とは、定年に伴い新たな契約を結ぶことであるとご説明しましたが、有給休暇については注意が必要です。
有給休暇は、6ヵ月以上継続的に勤務することを要件として発生し、勤続年数が長くなるにつれて、与えられる日数も増加します(最大20日)。
そこで、定年後の再雇用者に付与される有給休暇の日数について、定年前の勤続年数を含めるべきか、という問題があります。
法律の解釈では、「継続勤務」とは、「労働契約の存続期間=在籍期間」のことを意味します。
そして、労働契約が存続しているかどうかの判断は、「勤務の実態に即し実質的に判断すべきもの」であるとされています(昭和63年3月14日基発150号)。
そして、定年退職による退職者を引き続き嘱託などの身分で再雇用している場合は、形式的にはいったん契約が終了しているものの、実質的には同じ人が同じ会社に雇われ続けているのですから、労働契約が存続していると考えられ、継続勤務をしているものと扱われます。
したがって、有給休暇の日数を判断するに際しては、再雇用によって勤続年数をリセットせずに、定年前の勤続年数も含めることに注意してください。
.png)

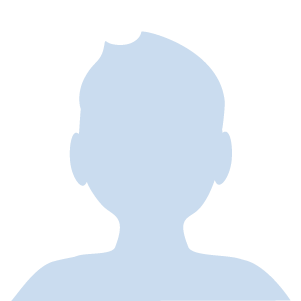


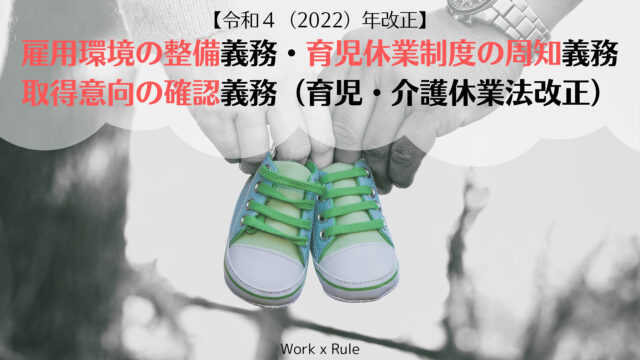

.png
)
.jpg)









